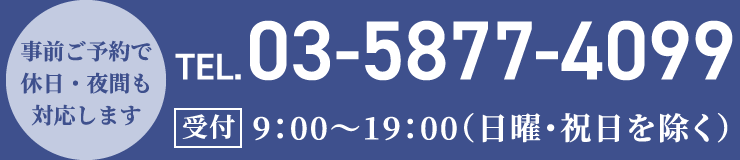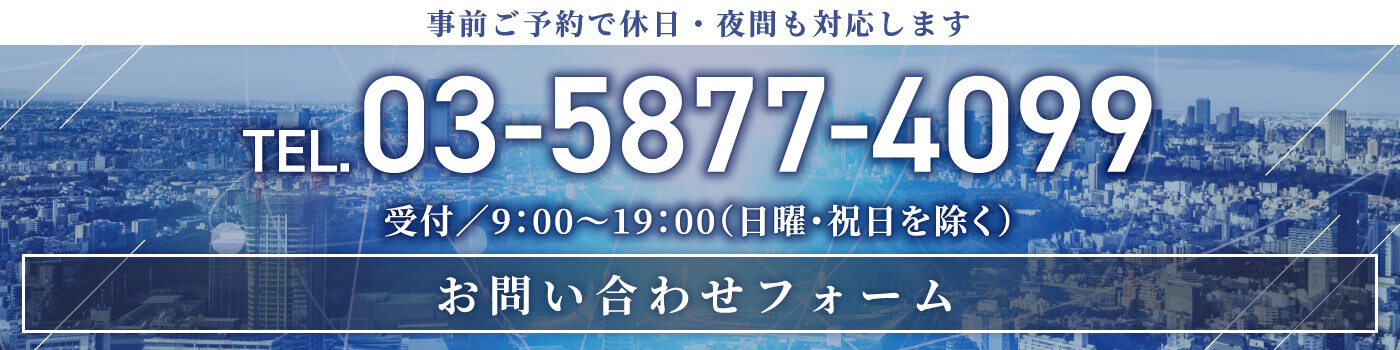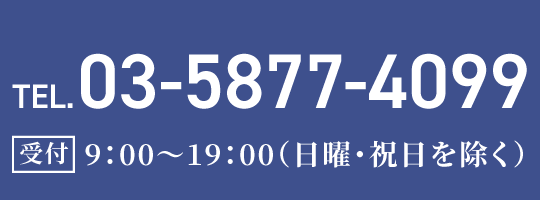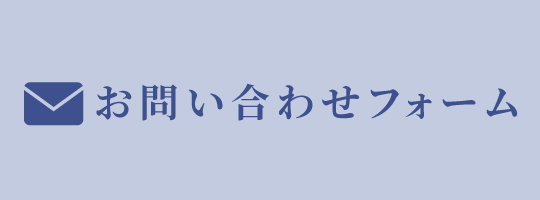Archive for the ‘広告関連法務’ Category
商品説明とは異なる試験が実施されていたケース
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 商品説明とは異なる試験が実施されていたケース
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①ダイエット効果を標ぼうする商品に関して、試験報告書が提出されたが、商品で標榜するダイエット効果について実証された内容と当該広告表示の内容が著しく乖離していたケース
②特段の運動や食事制限をすることなく摂取するだけでダイエット効果が得られることを標ぼうする商品に関して、裏付けとして試験報告書が提出されたが、試験内の被験者に対して実際には運動や食事制限の介入指導が行われていたケース
以上のようなケースでは、商品の成分効果と裏付けとなる実験が結びついておらず、商品の効果を示すことにとっては意味のない裏付け資料となってしまいます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
論文や試験内容に問題がある場合
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 論文や試験内容に問題がある場合
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①商品の成分に関する研究論文が裏付け資料として提出されたが、当該論文における被験者の成分摂取量と商品に含まれる量が著しく乖離しており、その商品を摂取することによる効果を示すものではなかったケース
②商品の成分に関する試験報告書が提出されたが、あくまでも動物実験データであって、人体への有効性を示すものではなかった。
以上のようなケースでは、商品の成分効果と裏付けとなる実験における結果が結びついておらず、商品の効果を示すことにとっては意味のない裏付け資料となってしまいます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
商品と提出された資料の効果が適切に対応していない場合
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 商品と提出された資料の効果が適切に対応していない場合
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①当該商品に含まれる成分に関してウェブサイト上の情報をまとめた資料が提出されたが、表示された本件商品自体の効果を実証するものではなく、裏付け資料としての意味合いがない資料であったケース
②当該商品に含有される成分に関する研究論文が提出されたが、その成分に関する一般的な記述が記載されているにすぎず、当該商品の効果を実証するものではなかったケース
以上のようなケースでは、資料に記載されている成分が適切に商品に含有されて効果が表れていれば問題ありませんが、商品の効果として別の効果が表れている場合には意味のない裏付け資料となってしまいます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
試験報告書が資料としての信用性に乏しいと判断されたケース
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 試験報告書が資料としての信用性に乏しいと判断されたケース
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①試験報告書が提出されたが、当該試験において対照品として用いられた物品が、当該商品とは全く別の商品であったケース(特定成分の効果を検証する試験を行う場合は、その特定成分を含む試験品と、その試験品からその特定成分のみを除外したものを対照品とする必要があるとされています。)
②ダイエット商品に関し、当該商品を用いた試験報告書が提出されたが、その試験における被験者の選定が恣意的であったケース
以上のようなケースでは、①はそもそも試験としての適切性が全くないと言えますし、②については形式面はさておき、実質的には試験としての適切性を欠いたものと考えられるところです。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
資料としての信用性が乏しいケース
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 資料としての信用性に乏しいケース
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①該当の成分に関してウェブサイト上で集められる程度の情報や、レビューの内容をまとめたものにすぎないケース
②商品の原材料の効果に関する文献を提出したものの、査読者のいる学術誌に掲載された文献ではなく、専門家の一般的な見解等信用性に足るものとは認められないものであったケース
③ダイエット商品に関して、商品を用いた試験の報告書が提出されたが、当該試験の具体的な被験者の食事内容やカロリー摂取量が記録されていなかったケース
以上のようなケースでは、根拠としての信用性が乏しく、消費者庁に提出した場合でも合理的な根拠は認められず、優良誤認表示であるとの認定は避けられないところです。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
著しく人を誤認させる表示とは
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。
1 「著しく」人を誤認させる表示
健康食品の広告表示の規制に関しては、通常、売買では売主がいわゆるセールストークを行いますので、ある程度の誇張表現が利用されることは規制の対象としておりません。
その一方で、健康増進法第65条第1項においては、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示を行うことについては規制対象としております。
そのため、具体的に何が規制の対象となる「著しく」に該当するかの判断基準が重要となりますが、消費者庁の公表資料では、例えば、一般消費者が、当該健康食品を摂取した場合に実際に得られる真の効果が広告表示に記載されたとおりではないことを知っていれば、その食品に誘引されることは通常ないと判断される場合は、「著しく」に該当する旨が説明されています。
要するに、そのことを知っていれば買わなかったのに知らなかったから買ってしまった、というようなケースであり、刑事上も詐欺行為に該当するようなケースが想定されているようです。しかしながら、ここまではいかずとも、例えば、そのことを知っていれば買ったかどうかわからない(多分買わなかっただろう)、というような微妙な場合にどのように判断すべきかは、個別の事情を踏まえて判断しなければならず、なかなか線引きとしては難しいところです。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
アフィリエイターが広告表示の規制対象者となるかどうか
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。
1 アフィリエイターが広告表示の規制対象者となるかどうか
健康食品の広告表示の規制に関しては、「アフィリエイターだから責任は発生しない」、等の考えを持っていらっしゃる方が一定数存在します。
確かに、景品表示法において広告表示の規制対象となるのは当該商品やサービスを供給する事業者ですので、その他の者にあたるアフィリエイターは原則として規制の対象とはなりません。
しかしながら、健康増進法上は、広告表示の規制対象を限定しておりませんので「何人も」対象となります。そのため、健康増進法上は、アフィリエイターも広告表示の規制対象者となりえる点には注意が必要です。
また、反対に、アフィリエイトサイトにおいて、虚偽誇大表示等に当たる内容の広告表示が行われた場合において、広告主がその表示内容を具体的に認識していないときであっても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず他の者であるアフィリエイターに表示内容の決定を委ねているケース等一定の場合には、広告主が広告表示規制の対象となる点にも注意が必要です。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
健康食品の広告表示の規制対象者
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。
1 健康食品の広告表示の規制対象者
健康食品の広告表示の規制に関しては、「自分は広告主ではなく、単なる広告媒体の事業者であるから関係ない」、「アフィリエイターだから責任は発生しない」、等の考えを持っていらっしゃる方が一定数存在します。
確かに、景品表示法において広告表示の規制対象となるのは当該商品やサービスを供給する事業者ですので、その他の者は原則として規制の対象とはなりません。
しかしながら、健康増進法上は、広告表示の規制対象を限定しておりませんので「何人も」対象となります。
このように、広告表示の規制といっても複数の法律が関係する場合には、単に景品表示法の規制だけを念頭に置いてしまうと思わぬところでミスをすることになりがちですので十分注意する必要があります。
昔は、広告主が新聞や雑誌等決まった媒体に広告を出すという典型的な方法が大半を占めており、広告表示の規制対象者が誰であるのかを注意する必要は必ずしも高くはなかったようですが、昨今はインターネットやSNS等の幅広い利用の結果、広告表示の規制対象者に該当するかどうかについても慎重に検討することが必要となっております。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
商品への間接的な誘引の表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。
1 直接的な商品の表示ではない場合にもご注意ください
商品名を広告において直接表示しない場合であっても、広告における説明文などによって特定の商品に誘引すると認められるときには、景品表示法及び健康増進法の規制対象となる「表示」に該当します。
①特定の食品や成分の健康保持増進効果等を説明している場合でも、当該説明付近にその食品の販売業者の連絡先などを目につきやすい形で記載しているケース
②特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者に対し、特定の商品に関する冊子や当該商品の無料サンプルを提供するなど、複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を一般消費者に対して誘引していると認められるケース
③ブランド名を介して、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告表示を読んだ一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるケース
以上のようなケースは、事業者にとっては用いやすい方法ではありますが、景品表示法や健康増進法において広告規制の対象となる「表示」に該当しますので十分に注意が必要です。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
新聞記事、専門家の談話などを引用又は掲載することにより表示するもの
昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。
ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。
最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。
本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。
1 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示するもの
健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『健康保持増進効果等』を暗示的又は間接的に表現するものについても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。
そしてここには、新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話やアンケート結果、学説、体験談などを引用又は掲載することにより表示するものも含まれることになります。
例えば、
A県在住のBさん(●歳)の体験談
「商品Cを3か月間毎朝続けて食べたら、3ヶ月間で10㎏痩せました。」
D医科大学E教授のコメント
「発がん性物質を与えたマウスに成分Fの抽出成分を食べさせたところ、何もしなかったマウスよりもかなり低い発ガン率だったことが学会で発表されました」
といった表現には注意が必要です。
2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください
健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。