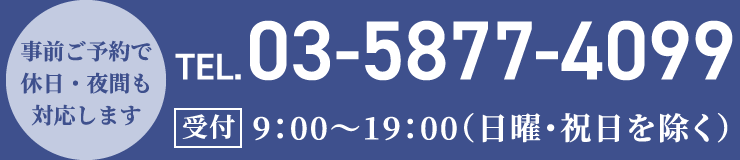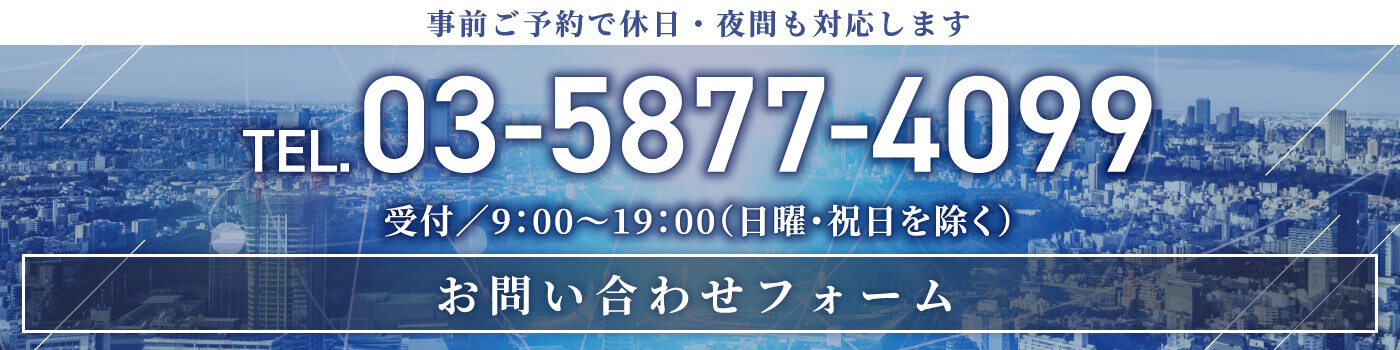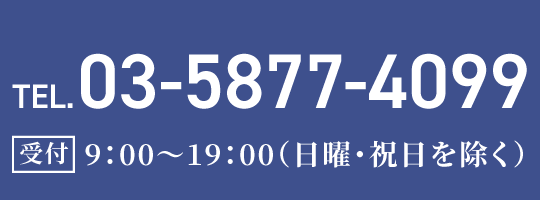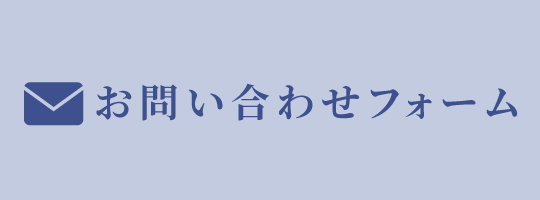「おすすめランキングNo.1!」「口コミ評価4.9点」「ユーザー満足度98%」──
レビューや比較サイトは、消費者が商品・サービスを選ぶうえで重視する情報源です。その信頼性の高さゆえに、企業も広告施策として活用するケースが増えています。
しかし、企業が関与しているにもかかわらず、あたかも中立・第三者の意見であるかのように見せる表示は、景品表示法違反(ステルスマーケティング)に該当するリスクがあります。 また、ランキングやスコア表示に合理的な根拠がない場合も、「優良誤認表示」として問題視されます。
このページの目次
1 なぜレビュー・比較サイトが規制対象になるのか?
一見、企業が直接関与していないように見えるレビュー・比較サイトですが、以下のようなケースでは「広告表示」として扱われ、景品表示法の規制対象となります。
①実質的に企業が運営・制作を委託している比較サイト
②掲載順や点数を金銭の対価で操作している(=広告)
③第三者評価のように見せかけながら、PR目的の情報だけが並んでいる
このような「企業の表示であることが消費者にとって明瞭でない」ケースは、2023年に施行されたステマ規制強化(景表法改正)により、明確に違法表示と判断される可能性が高くなっています。
2 比較ランキングの「順位」「スコア」の根拠が必要
比較サイトでよく見かける「ランキング表示」「点数評価」「おすすめNo.1」などは、消費者にとって非常に影響力のある表現です。だからこそ、それに客観的な根拠や合理的な評価基準がなければ、優良誤認表示に該当するおそれがあります。
NG例としては、
①掲載企業からの広告料でランキング順位を決定
②評価スコアの算出方法が不明(基準や重みづけが非公開)
③実在しないユーザーのレビュー・口コミを掲載
ランキングや点数の表示には、評価項目・基準・集計方法・調査時期などを明記し、広告主がその妥当性を説明できる状態にあることが必要です。
3 第三者を装った「おとりサイト」「体験談サイト」に注意
以下のような形式は、過去に消費者庁から措置命令が出された事例もあります。
①「主婦が自腹で試してみた!」と題し、実際には企業が制作した記事
②「ユーザーの本音レビュー」として、報酬提供を受けたインフルエンサーの投稿を転載
③「比較した結果◯◯がベスト」とするが、選定根拠は企業からの提供資料のみ
このような表示を消費者が「中立・第三者の評価」と誤認する構成にすると、明確な不当表示とされる可能性があります。
消費者にとって、比較・レビュー情報は「信用できる第三者の声」であり、その信頼を裏切るような操作や隠れた広告表示は、ブランドの信頼そのものを損ねかねません。
だからこそ、“中立性”や“透明性”を前提にした表示と運用が、今後のマーケティングには不可欠です。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。