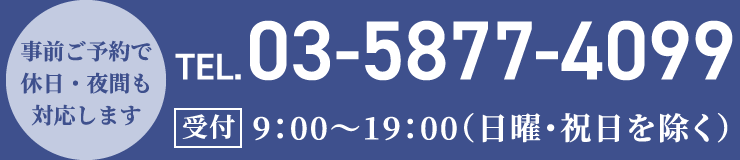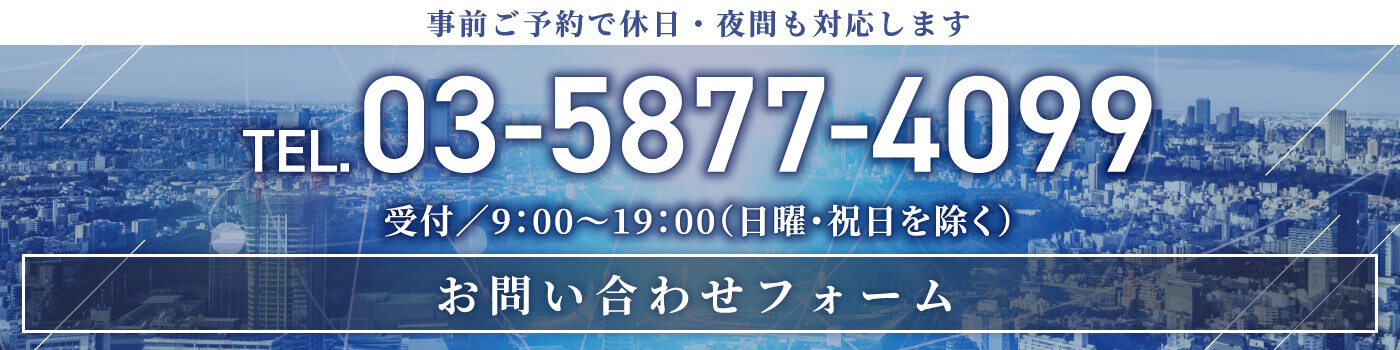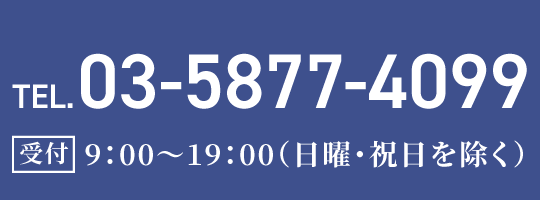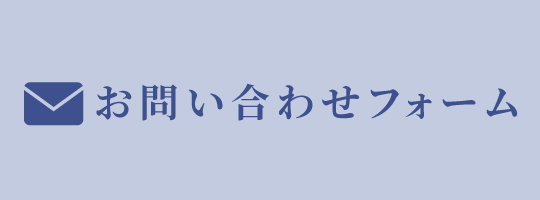本日は、「機能性表示食品」に関連する広告や表示上の注意点を、消費者庁のガイドラインをもとに概要をご説明します。
昨今、改めて機能性表示食品が問題となるケースが出ておりますので、事業者は、消費者に誤解を与えないように、法律を正しく理解し運用する必要があります。
このページの目次
1 そもそも機能性表示食品とは?
機能性表示食品とは、科学的根拠に基づいて健康維持や特定の機能を表示できる食品です。これは『消費者庁』に届け出を行うことで、このような表示が可能になります。
しかしながら、『医薬品』ではありませんので、病気の治療や予防を謳うことは許されません。
2 適切な広告表示のための留意点『景品表示法の禁止事項』
①優良誤認表示の禁止
商品が実際よりも著しく優れているかのように表示することは禁止されています。
②合理的な根拠
消費者庁は、広告表示の裏付けとなる科学的根拠の提出を求めることができます。
根拠を示せない場合、その広告は「不当表示」とされますので、常に合理的な根拠の存在は確認する必要があります。
3 適切な広告表示のための留意点『健康増進法の留意点』
①疾病の治療・予防効果を謳わない
「この食品を飲めば糖尿病が治る!」といった疾病治療や予防を示唆する表示は、健康増進法に違反します。
②正確な情報の提供
届け出た機能性表示内容から逸脱しないよう、科学的根拠に即した正確な表示が求められます。
4 消費者を誤認させないための表示基準
①届出表示の範囲を守る
機能性表示食品として届け出た内容以外を強調することは、消費者の誤解を招くため、厳しく制限されています。
②医薬品や特定保健用食品と混同しない表示
医薬品のように「病気が治る」と誤認させる表現は禁止ですし、「消費者庁長官の許可を受けた」と誤解されるような文言も避けるべきです。
5 事業者として心がけるポイント
①事実を正確に表示する
②科学的根拠を確保する
③法律を確認する
6 機能性表示食品を取り扱う事業者は改めてご注意ください
機能性表示食品の広告や表示には、景品表示法と健康増進法等による厳しいルールがあります。
事業者は消費者に対して正確な情報を提供し、誤解や過度な期待を与えないよう注意することが求められます。また、意図せずに違法な広告表示をしてしまうと、一般消費者からは『悪徳業者』等とのレッテルを貼られてしまうリスクがありその後の事業の運営にも大きな影響があります。
少しでも不安や疑問があれば、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。