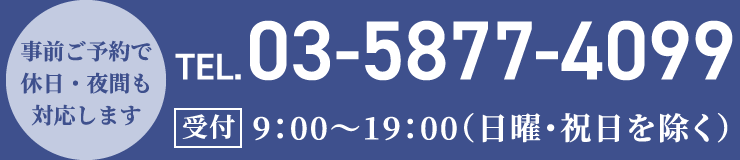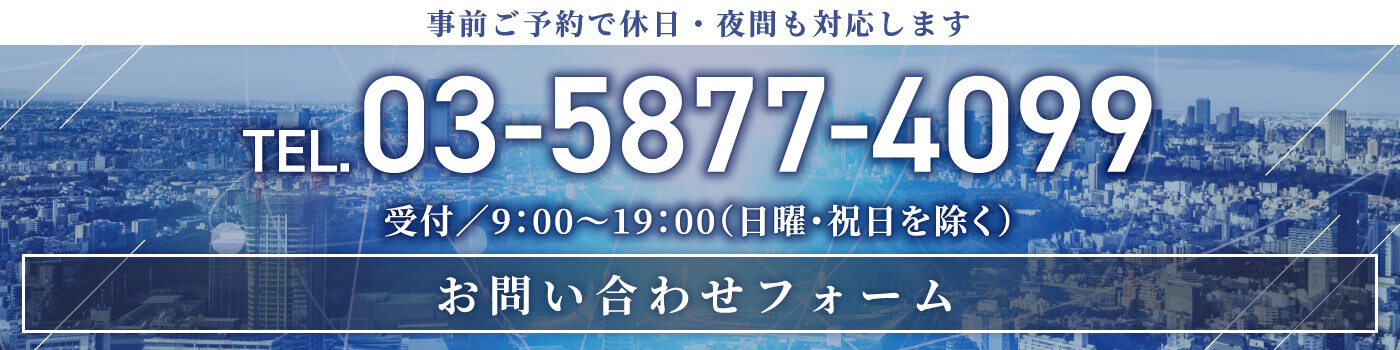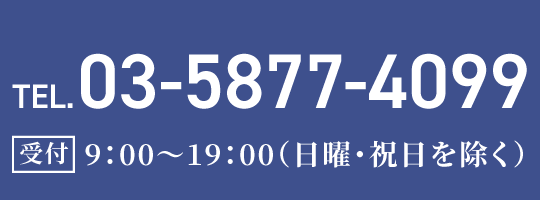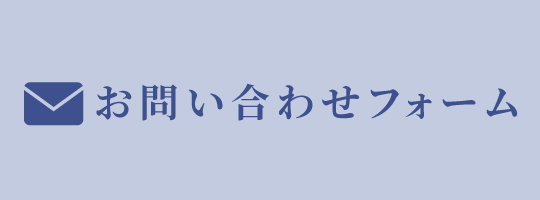Archive for the ‘広告関連法務’ Category
「今だけお得」を繰り返していませんか?カウントダウンタイマーや「閉店セール」商法の法的リスク
「キャンペーン終了まであと30分!」 Webサイトを訪れるとカウントダウンタイマーが作動し、焦って購入ボタンを押す。しかし、翌日同じサイトを見たら、またタイマーがリセットされて「あと30分」になっていた…。
このような手法は、消費者の射幸心や焦燥感を煽るマーケティングテクニックとして一部で流行しましたが、法的には「有利誤認表示」にあたる極めてグレー(というよりブラック)な行為です。
1 「期間限定」の嘘
「○月○日まで」、「あと○時間」という限定表示を行う場合、その期間を過ぎれば、実際に価格を上げる(または販売を終了する)必要があります。
もし、期間終了後も同じ価格で販売を続けていたり、すぐに同条件のキャンペーンを再開したりしていれば、「期間限定」という表示は嘘であったことになります。
消費者は「今買わないと損をする」と誤認して購入しているため、景品表示法違反となります。
2 「打消し表示」があれば許される?
「※キャンペーンは予告なく延長する場合があります」「※好評につき期間延長」といった注釈(打消し表示)を小さく書いておけば大丈夫だと思っていませんか?
消費者庁は、こうした打消し表示について「一般消費者が容易に認識できない場合」や「強調表示(メインの宣伝文句)と矛盾する場合」は無効であると判断しています。
メインで「本日終了!」と煽っておきながら、小さく「延長するかも」と書くのは矛盾しており、免罪符にはなりません。
3 過去の処分事例
実際に、紳士服チェーンの「閉店セール」や、オンライン英会話スクールの「期間限定キャンペーン」などで、実際には長期間にわたり継続して行われていたとして、消費者庁から措置命令が出された事例があります。
一度措置命令が出ると、記者会見で社名が公表され、「嘘つき企業」というレッテルを貼られてしまいます。昨今の社会情勢を踏まえますと、いったんこのようなレッテルが貼られてしまうと引用をよく変えることは至難の業でしょう。
マーケティングにおいて「限定性」は強力な武器ですが、嘘をついてはいけません。
「本当に期間を区切る」か、あるいは「期間を区切らずに常時特典とするか」の二択です。誤解を招くLPになっていないか、弁護士によるチェックを受けることをお勧めします。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
その「半額セール」は違法かも?二重価格表示の落とし穴
ECサイトやチラシでよく見る「通常価格10,000円のところ、今だけ5,000円(50%OFF)!」という表示。 これを「二重価格表示」といいます。消費者の購買意欲を刺激する強力な手法ですが、比較対象となる「通常価格(または当店通常価格)」の実態がない場合、景品表示法違反(有利誤認表示)となります。
いわゆる「定価の架空設定(上げ底表示)」ですが、ルールを知らずに設定してしまっている事業者が後を絶ちません。
1 「通常価格」と認められるための「実績」
ただ単にシステム上の定価欄に数字を入れただけでは、「通常価格」とは認められません。 消費者庁の「二重価格表示に関するガイドライン」では、比較対照価格(元値)として表示するためには、「最近相当期間にわたって販売された実績」が必要とされています。
具体的には、以下のいずれかの条件(「2週間ルール」などと呼ばれます)を満たす必要があります。
①過去8週間のうち、過半(4週間以上)の期間、その価格で販売されていたこと。
②直近2週間、その価格で販売されていたこと(ただし、販売期間が短い場合)。
つまり、「販売開始初日から『通常1万円→今だけ5千円』」と表示することは、1万円での販売実績がないため違法です(メーカー希望小売価格がある場合を除く)。
2 セール終了後の価格戻し忘れ
よくあるトラブルが、「期間限定セール」が終わったのに、システムの設定ミスや担当者の失念で、二重価格表示が残ってしまっているケースです。 あるいは、常に「50%OFF」と表示し続けている場合、「50%OFFの価格」が実質的な「通常価格」となり、もはや割引とは言えなくなります。これも有利誤認表示として処罰対象です。
3 ECモールでの注意点
Amazonや楽天などのモールでは、二重価格を表示するための入力欄(参考価格など)がありますが、プラットフォーム側もコンプライアンスを強化しており、販売実績のない価格を入力すると自動的に非表示になったり、アカウント健全性が低下したりする仕組みになっています。 また、行政処分を受けると、アカウント停止(垢バン)に直結し、売上がゼロになるリスクもあります。
「他社もやっているから」は通用しません。価格表示は、消費者が最も敏感な部分であり、競合他社からの通報も多い分野です。セールの計画を立てる際は、必ず「元値の根拠」を確認する習慣をつけてください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
「No.1表示」は危険?リサーチ会社のお墨付きがあれば大丈夫?
自社の商品を「業界No.1」「顧客満足度第1位」と宣伝することは、強力なマーケティング手法です。
しかし、近年、この「No.1表示」に対する消費者庁の監視が極めて厳しくなっています。リサーチ会社に依頼して取得したNo.1称号であっても、その調査方法が杜撰であれば、景品表示法違反(優良誤認表示)として措置命令や課徴金の対象となります。
1 狙われる「No.1」のカラクリ
最近問題視されているのは、実態を伴わないNo.1です。 例えば、「サイトのイメージ調査」と称して、商品を実際に使っていないモニターに対し、「この商品のサイトを見て、満足度が高そうだと思いますか?」とアンケートを取り、その結果をもって「顧客満足度No.1」と謳うケースです。
これは「使用者の満足度」ではなく「Webサイトの印象」に過ぎません。それにもかかわらず、あたかも「多くのユーザーが使って満足している」かのように宣伝することは、消費者を騙す行為(優良誤認)にあたります。
2 適法なNo.1表示の3要件
適法にNo.1を謳うためには、以下の3つの条件を満たす「合理的な根拠」が必要です。
①客観的な調査であること
恣意的な調査(自社に都合の良い回答者だけを選ぶなど)ではないこと。第三者機関による調査が望ましいですが、その機関が公正である必要があります。
②調査結果と表示内容が正確に対応していること
「売上No.1」なのか「満足度No.1」なのかを正確に書くこと。「イメージ調査」なのに単に「No.1」と書くのはNGです。
③比較対象が明確であること
「競合他社○社と比較して」など、どの範囲でのNo.1なのかを明記すること。
3 課徴金のリスク
No.1表示が嘘(不当表示)であると認定された場合、その広告を行っていた期間の売上額の3%にあたる「課徴金」が課される可能性があります。
売上が1億円あれば、300万円の罰金です。さらに、社名公表によるブランド毀損は計り知れません。
「リサーチ会社が大丈夫だと言ったから」という言い訳は、行政には通用しません。
最終責任は広告主にあります。 No.1表示を行う際は、その調査設計が景表法のガイドライン(不実証広告規制)に耐えうるものか、事前に弁護士によるチェックを受けることが、企業防衛の要となります。
少しでもご不安な点がある場合には、すみやかに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
健康食品の広告で「痩せる」「治る」は絶対NG。薬機法の壁と問題とならないための表現テクニック
「飲むだけで-10kg」「血液サラサラ」「免疫力アップ」
健康食品やサプリメントのLP(ランディングページ)で、このような表現を使っていませんか? もし使っているなら、あなたの会社はいつ薬機法違反で逮捕されてもおかしくない状態です。
健康食品は、法律上はあくまで「食品」です。
「薬」ではありません。そのため、医薬品のような「効能効果(病気が治る、身体機能が変化する)」を標榜することは、「未承認医薬品の広告」として厳しく禁止されています。
1 NG表現の具体例(薬機法違反)
以下の表現は、たとえ事実(体験談やデータ)があったとしても、広告で使用することはできません。
①疾病の治療・予防:「癌が治る」「花粉症対策」「高血圧の方に」
②身体の機能・構造への影響:「脂肪燃焼」「デトックス」「疲労回復」「バストアップ」「アンチエイジング」
③医薬品的な用法用量:「食前に3粒」「寝る前に」
これらを書くと、「医薬品としての承認を受けていないのに、医薬品のような効果を謳っている」として、警察による捜査や、行政からの措置命令の対象となります。
2 「個人の感想です」は無意味
よくある「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」という打ち消し表示。 これさえ書けば許されると思っている方が多いですが、消費者庁や行政の判断は「打ち消し表示は無効」です。
メインのキャッチコピーで効能効果を謳っている以上、小さな注釈で否定しても、消費者の誤認は防げないと判断されます。体験談(UGC)であっても、事業者が広告として選別・掲載している以上、責任は事業者にあります。
3 どのように表現すればいいのか?
薬機法を遵守しつつ、商品の魅力を伝えるには「言い換え」の技術と法的知識が必要です。
①「痩せる」→「健康的な体づくりをサポート」「運動と併用して理想のスタイルへ」
②「若返る」→「年相応の美しさを」「ハリのある毎日を」
③「疲労回復」→「元気をチャージ」「朝の目覚めをスッキリ」
ただし、これらの言い換えも、前後の文脈や写真(ビフォーアフター等)との組み合わせによっては違法となります。「暗示」や「ほのめかし」も規制対象だからです。 当事務所では、広告の訴求力を維持しながら、薬機法・景表法のリスクを回避する「広告リーガルチェック」を行っています。「この表現は攻めすぎか?」「代替案はないか?」と迷った際は、公開前に必ず弁護士へご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
インフルエンサー施策で広告主が処分される!「PR」表記の基準と契約書で見直すべきポイント
2023年10月1日から、景品表示法の指定告示として「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」、いわゆる「ステマ(ステルスマーケティング)規制」が施行されました。
これまで、日本の法律では「嘘を書くこと(優良誤認・有利誤認)」は規制されていましたが、「広告であることを隠すこと」自体を直接罰する法律はありませんでした。
しかし、この改正により、広告であることを隠して口コミや感想を装う行為は、明確な違法行為となります。
1 処罰されるのは「広告主」だけ
今回の規制の最大の特徴は、規制対象が「広告主(事業者)」に限られるという点です。
ステマを行ったインフルエンサーやアフィリエイター自身は処罰されません。あくまで「広告主が書かせた」とみなされ、依頼元の企業が措置命令(社名公表など)の対象となります。 「インフルエンサーが勝手にPR表記を忘れた」という言い訳は通用しません。広告主には、投稿内容を管理・監督する責任があるからです。
2 どこからが「ステマ」になるのか?
消費者庁の運用基準では、「事業者が表示内容の決定に関与した」と認められる場合、それは広告(事業者の表示)とみなされます。
①金銭の授受がある場合:もちろん広告です。「PR」「広告」「プロモーション」等の表記が必須です。
②商品無償提供(ギフティング)の場合:ここが重要です。「商品をあげるから、良かったら投稿してね」というケースでも、過去のやり取りや関係性から、実質的に投稿を依頼しているとみなされれば規制対象になります。
③社員の投稿:自社の社員が、身分を隠して自社商品を絶賛する投稿もステマに該当します。
3 企業が今すぐやるべき3つの対策
行政処分を受けないために、以下の対策を講じてください。
①過去の投稿の洗い出し
規制は施行日(2023年10月1日)以降に「掲載されている」もの全てに適用されます。数年前の投稿であっても、現在閲覧可能であれば削除または修正(PR表記の追記)が必要です。
②契約書の改訂
インフルエンサーや代理店との契約書に、「景表法およびステマ規制の遵守」を明記し、PR表記の義務付けと、違反時の損害賠償条項(または投稿削除権限)を盛り込む必要があります。
③レギュレーションの配布
「#PR を1行目に入れる」「動画の中で広告であることを口頭で伝える」など、具体的な投稿ルール(レギュレーション)を作成し、インフルエンサーに周知徹底してください。
ステマ規制は「知らなかった」では済まされません。SNSマーケティングを行う企業様は、一度弁護士によるリーガルチェックを受けることを強くお勧めします。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
健康食品・サプリメント広告の分水嶺:効能効果表現のNG例
健康食品やサプリメントは、人々の健康意識の高まりとともに市場が拡大していますが、これらの商品の広告は、薬機法(医薬品医療機器等法)の規制との境界線上で、慎重な判断が必要です。
健康食品は「食品」であり、本来は薬機法の直接的な規制対象外です。
しかし、その広告表現が「医薬品的な効能効果」を謳ってしまうと、国から未承認の医薬品とみなされ、行政処分や刑事罰の対象となります。
企業の法務担当者や経営者は、この「医薬品と誤認させるか否か」という線引きを正確に理解しておく必要があります。
1 薬機法における「医薬品的な効能効果」とは?
薬機法が禁止する「医薬品的な効能効果」とは、主に以下の二つの目的を持つ表現です。
(1)疾病の治療・予防を目的とする表現
病気の診断、治療、予防を目的とする表現は、医薬品にのみ許されています。
健康食品の広告でこれらの表現を使うと、消費者はその商品が「薬のように病気を治してくれる」と誤認します。
NG例::「ガンを予防するサプリ」「高血圧を改善する」「アトピーの治療に」「胃潰瘍を治す」
(2)身体の構造や機能に作用する表現
人の身体の特定の構造や機能に対して、明確な改善、増進、変化を与えるといった表現も、医薬品的な効能効果とみなされます。
NG例: 「ホルモン分泌を促進し、若返る」「肝機能を回復させる」「細胞を活性化する」
2 広告表現の「グレーゾーン」を乗り越える鉄則
健康食品の広告においては、上記のような「直接的な表現」だけでなく、消費者に医薬品的な効能効果を「暗示させる表現」も規制の対象となります。この「暗示」こそが、最も難しい「グレーゾーン」です。
(1)鉄則1:標榜可能な効能効果のリストを厳守する
食品として許容される表現の目安として、例えば、健康の維持及び増進に資する目的や、栄養補給、美容に関する一般的な表現に留めることが基本です。
特に、「症状名」や「器官・部位名」を直接的に結びつける表現は避けるべきです。
(2)鉄則2:体験談・ビフォーアフター写真の制限
口コミや体験談は、個人の感想であっても、事業者がそれを広告に利用する以上、広告表現の一部として薬機法の規制対象となります。
NG例::「このサプリで重い更年期障害が治った」といった医薬品的な効能を主張する体験談。
NG例::使用前後の病状の変化を写真で比較する「ビフォーアフター」画像。
体験談は、食品の範疇を超えた効果(例:治療効果)を消費者に強く暗示するため、たとえ「個人の感想」と明記しても、薬機法違反となるリスクが極めて高いです。
(3)鉄則3:名称・形態・記号による暗示の排除
広告文言だけでなく、商品名やパッケージデザイン、さらには使用する記号やイラストにも注意が必要です。
NG例:商品名に「○○治療薬」「飲む注射」といった医薬品を連想させる名称を用いる。
NG例:白衣を着た医師や、注射器、医療機器のイラストなど、医療行為を連想させる画像を使用する。
3 まとめ:生命・健康に関する表現は「最も厳格に」
健康食品やサプリメントは、景品表示法だけでなく、国民の生命・健康の保護を目的とする薬機法による最も厳格な規制を受けます。
企業の法務担当者や経営者は、広告を作成する際に、「誰が読んでも、この商品が『薬』ではないと理解できるか」という視点に立ち、安易な効果の誇張や暗示を排除し、「正確な情報提供」に徹することが、刑事罰を含む致命的なリスクを避けるための唯一の方法です。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
薬機法における広告規制の基本
企業の法務担当者や経営者にとって、景品表示法と並んで理解が必須となるのが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称「薬機法」です。
薬機法は、医薬品や化粧品などの安全性と有効性を確保するための法律ですが、その規制は製品の製造・販売に留まらず、それらの広告表現にまで及びます。特に健康食品や美容関連商品を扱う企業は、薬機法違反による行政処分や逮捕のリスクがあるため、厳格なコンプライアンス体制が求められます。
1 薬機法の目的と規制対象
薬機法が規制するのは、主に以下の4つのカテゴリーの商品です。
①医薬品(薬局で購入する薬、医師の処方薬など)
②医薬部外品(特定の目的を達成するために使用されるもの。例:薬用化粧品、育毛剤、制汗剤など)
③化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増すもの。例:ファンデーション、シャンプー、一般的な化粧水など)
④医療機器(病気の診断、治療、予防に使用されるもの。例:ペースメーカー、コンタクトレンズ、家庭用マッサージ器など)
薬機法の目的は、これらの製品の「承認されていない効能効果」や「安全性を保証しない」広告によって、消費者の健康被害や不利益が生じることを防ぐことにあります。
2 広告規制:誇大広告等の禁止
薬機法における広告規制の核心は、誇大広告等の禁止にあります。
具体的には、以下の表示を禁止しています。
①虚偽・誇大な表現の禁止
効能効果、安全性について、事実に反する、または著しく誇大な表現。
「絶対安全」「副作用なし」「確実に治る」**などの断定的な表現は厳しく禁止されます。
②承認等を受けていない効能効果の表示の禁止
医薬品等が、国から承認された効能効果の範囲を超えた内容を表示すること。
3 健康食品・サプリメント広告への適用
健康食品(サプリメント)は、医薬品でも化粧品でもない「一般食品」に分類されます。
しかし、健康食品の広告で医薬品的な効能効果(例:「胃潰瘍を治す」「ガンを予防する」)を謳った場合、その健康食品自体が「未承認の医薬品」であるとみなされ、薬機法違反と判断されます。
薬機法は、消費者の生命と健康を守るための法律であり、その規制は非常に厳格です。「少し盛るくらいなら大丈夫」という安易な判断は、刑事罰を含む致命的なリスクを企業にもたらします。
薬機法を踏まえた広告表現に関して少しでも不安な点がある場合は、まずはお問合せください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
景品表示法違反の罰則とペナルティ:措置命令・課徴金制度の仕組みと実務対応
これまで景品表示法(景表法)が規制する「優良誤認表示」「有利誤認表示」「景品規制」など、具体的な違反類型を解説してきました。しかし、企業にとって最も深刻な問題は、違反が発覚した場合に課されるペナルティです。
景表法に違反した場合、単なる行政指導で終わるのではなく、「措置命令」や「課徴金納付命令」といった重い処分が待っています。企業の存続や社会的信用に直結するため、法務担当者や経営者は、これらの制度の仕組みと、違反が発覚した際の実務対応を理解しておく必要があります。
1 措置命令制度:違反行為の「ストップ」と「再発防止」
景表法違反が認められた場合、消費者庁が行う可能性があるのが措置命令です。これは、違反行為を是正し、再発を防ぐための命令です。
(1)措置命令の内容(企業に課される義務)
①違反行為の停止:現在行っている不当な表示や景品の提供を直ちにやめること。
②再発防止策の実施:今後の違反を防ぐための社内体制や広告審査フローを確立すること。
③誤認排除の周知徹底:消費者に対して、過去の広告が不当なものであったことを新聞やウェブサイトなどで公表し、誤解を解消すること。
特に「周知徹底」は、企業名が広く公表されることを意味し、ブランドイメージと信用に決定的なダメージを与えます。措置命令は、企業のコンプライアンス体制そのものの見直しを強制する、厳しい行政処分です。
2 課徴金制度:不当に得た利益の剥奪
措置命令と並び、企業に金銭的かつ最も大きな痛手を与えるのが課徴金納付命令です。
これは、不当な表示によって消費者を誘引し、企業が不当に得た経済的利益を国が剥奪することを目的とした制度です。
3 法務・経営者が取るべき実務対応
違反が疑われる、または発覚した際の対応は、企業リスクを最小限に抑える上で極めて重要です。
(1)初動対応の徹底
①表示の即時停止:疑義が生じた広告表現やキャンペーンは、消費者庁の調査を待たずに直ちに停止します。
②事実関係の調査:表示内容の根拠資料、広告制作過程、関与部署(マーケティング、広報、法務)の関与状況など、事実関係を迅速かつ正確に把握します。
③自主申告の検討:課徴金の減額を視野に入れ、速やかに弁護士等の専門家と連携し、自主申告を行うかどうかを検討します。
(2)予防策としての体制構築
最も重要なのは、違反を起こさないための予防体制の構築です。
措置命令における「再発防止策」としても求められる内容です。
①広告審査の権限強化:法務部門が関与する広告審査フローを必須とし、根拠資料のチェックなしに広告を公開させない体制を確立する。
②エビデンス(根拠資料)の管理:広告に使用するデータや調査結果は、正確性、最新性、公正性を確保した上で、最低3年間は厳重に保管する。
③全社的な教育:経営層から一般社員まで、景表法の基本的な知識と、「消費者の誤解を招かない誠実な表示」の重要性に関する定期的な研修を実施する。
景表法違反は、単なる罰金ではなく、企業が積み重ねてきた信頼という無形の資産を破壊します。課徴金という金銭的リスクだけでなく、社会的信用の維持という観点からも、法務部門主導による広告コンプライアンスの徹底が、経営の最重要課題の一つであることを認識すべきです。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
打消し表示の法的有効性:消費者に伝わる表示の鉄則
広告には、スペースや時間の制約から、メインのメッセージを補足したり、条件を限定したりするために、小さな文字やアスタリスクで注意書きを付記することが頻繁にあります。これが打消し表示です。
法務担当者は、「*ただし、効果には個人差があります」といった打消し表示を入れれば、誇大広告のリスクを避けられると考えがちです。
しかし、景品表示法(景表法)の観点から見ると、打消し表示は万能の免罪符ではありません。不適切な打消し表示は、優良誤認表示を解消できず、かえって消費者を誤認に導くとして規制の対象となり得ます。
1 打消し表示の法的限界:「メインの誤認は解消できない」
打消し表示の役割は、メインの表示によって生じた消費者の誤解を解消すること、または重要な前提条件を補足することにあります。
しかし、景表法は、メインの表示がすでに「著しく優良であると誤認させる」レベルに達している場合、打消し表示をもってしてもその誤認は解消されないという立場をとっています。
【具体的なNG例】
メインのメッセージで「誰でも飲めば1週間で必ず-5kg!」と断定的に謳っているとします。これは、科学的根拠がない限り、優良誤認表示(不当表示)に該当します。この下に「*効果には個人差があります」と記載したところで、消費者はすでにメインの断定的なメッセージに強く影響を受けて購入を決断するため、不当表示は解消されないと判断されます。
打消し表示は、誤認が生じない程度の曖昧さや限定的な条件を補足する場合にのみ、有効性を持ちます。
2 打消し表示が有効となるための3つの要件
打消し表示が消費者の誤認を解消し、適法なものとして認められるためには、消費者庁が示す以下の3つの要件をクリアする必要があります。
これらは、「消費者に正しく伝わること」を担保するための鉄則です。
3 法務担当者が注意すべき打消し表示の実務
打消し表示を効果的かつ法的に安全に使用するために、法務部門は以下の実務的なリスクをチェックする必要があります。
(1)リスク1:情報量の多さによる「打ち消し効果の減衰」
打消し表示があまりにも長く、多くの情報を含む場合、消費者はそれを読み飛ばしがちになります。消費者の注意を分散させ、結果として重要な限定条件が伝わらないリスクが生じます。打消し表示は簡潔に、かつ本質的な限定条件のみを記載するようにすべきです。
(2)リスク2:スマホなど表示媒体による差異
パソコン画面では適切に見える文字の大きさや位置も、スマートフォンなどの小さな画面で表示した際に判読が困難になることがあります。すべての表示媒体において、要件2の「視認性」が確保されているかを検証しなければなりません。
(3)リスク3:景表法と特定商取引法との関係
特に定期購入やサブスクリプション広告において、解約条件や総額に関する表示は、景表法だけでなく特定商取引法の規制も受けます。特商法では、「最終確認画面」などにおいて、解除条件や価格に関する情報を誤認のおそれが無いように表示することが義務付けられています。この場合は、景表法の基準よりもさらに厳格な表示の明瞭さが求められます。
4 まとめ:打消し表示は「保険」ではなく「補足」
打消し表示は、あくまでメインの表現が適法であることを前提として、その適用範囲を正確に補足するための手段です。
誇大な広告表現を「免罪符」で合法化しようとする姿勢は、景表法の趣旨に反します。企業の法務担当者や経営者は、広告企画の段階から、客観的な事実に基づいた表現をメインとし、打消し表示は「消費者に正確な情報を提供する」ための最後の確認プロセスと位置づけるべきです。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
口コミ・体験談広告の法的リスク:消費者庁の見解と事業者がすべき対応
インターネット通販やSNSマーケティングにおいて、「お客様の声」や「使用者の体験談」といった口コミ形式の広告は、消費者の信頼を得る上で非常に強力なツールです。
しかし、その信頼性の高さゆえに、景品表示法(景表法)による規制の対象となりやすく、特に法務担当者にとっては注意が必要です。
1 リスク1:優良誤認表示となるケース
口コミ・体験談広告が優良誤認表示(景表法第5条第1号)となるのは、その体験談が商品の品質や効果について、実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる場合です。
これは、体験談が「個人の感想」であるかどうかにかかわらず、事業者が広告として利用する以上、表示責任を負うという原則に基づきます。
(1)根拠のない「最高の効果」の事例
特定の個人が「たった1日で5kg痩せた」「アトピーが完全に治った」といった過度な効果を主張する体験談を、事業者がそのまま広告に利用する場合、優良誤認と判断されます。
【判断のポイント】
①裏付けとなる合理的根拠の有無:事業者は、その体験談の内容が、科学的・客観的な根拠(データ)によって裏付けられる範囲内の効果であるかを、事前に確認する義務があります。
②例外的な効果の強調:多数の人が得られない極めて例外的な効果を、あたかも誰でも得られるかのように強調して表示することは、消費者の誤認を招きます。
(2)打消し表示の限界
優良誤認のリスクを回避するために、「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません」といった打消し表示を付記することが一般的に行われています。
しかし、前回の記事でも解説した通り、メインの体験談が過度な効果を謳っている場合、片隅に小さな文字で打消し表示をしても、消費者の誤認が解消されないと判断されれば、優良誤認表示として規制されます。打消し表示は、あくまで誤認を招く可能性を減らすための補完的な措置であり、広告内容の根拠の欠如を補うものではありません。
2 リスク2:ステマ規制となるケース
2023年10月に施行されたステマ規制(景表法上の指定告示)は、口コミ・体験談広告に対しても大きな影響を与えます。
(1)報酬が発生している場合の明示義務
企業がインフルエンサーやモニターに対して金銭や商品の提供(報酬)を行い、その対価として商品の使用感や体験談を投稿してもらう場合、その投稿は事業者の広告(宣伝)と見なされます。
このような場合、インフルエンサーなどの投稿者は、その投稿が「広告」「PR」「プロモーション」であることを、消費者が容易に判別できる位置に明記する義務があります。この明記がない場合、事業者はステマ規制違反として責任を問われます。
(2)自作自演・第三者装い型
事業者自身や、その従業員が、一般の消費者や匿名アカウントを装って自社商品・サービスの体験談を投稿する行為は、典型的なステマ規制違反です。
これは、事業者による表示であることを隠しているため、消費者がその意見を「公平な第三者の声」と誤認してしまい、「判別が困難な表示」に該当します。
3 投稿内容のモニタリングとエビデンス管理
外部委託先の投稿が、契約通りに広告表示の明記を行っているかを公開後も継続的にモニタリングしましょう。
また、広告に使用する全ての体験談について、その元の投稿内容、投稿者とのやり取り、報酬の有無などのエビデンス(証拠)を、措置命令を受けた際に提示できるよう適切に管理・保管しておくことが、事後的な対応において非常に重要となります。
口コミの力を借りる場合でも、最終的な責任は広告主である事業者が負います。「お客様の声だから大丈夫」という安易な考えは捨て、全ての体験談に「広告責任」が伴うことを認識する必要があります。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。