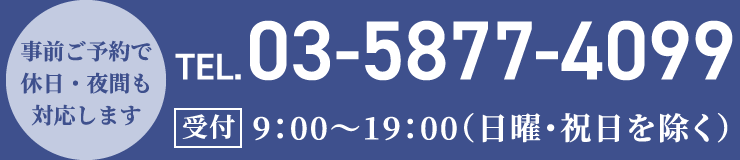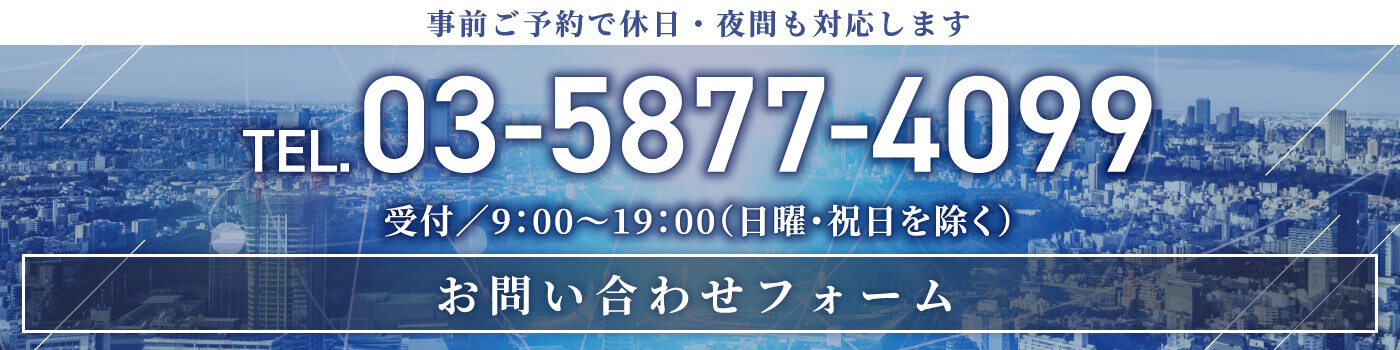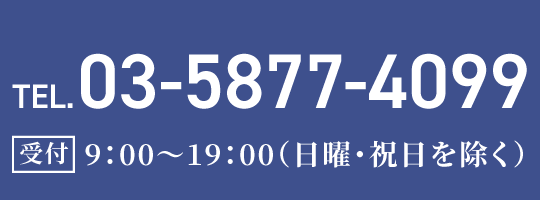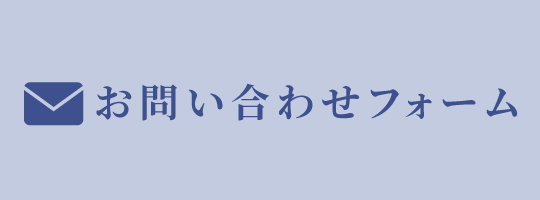景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。
このページの目次
1 「著しく」人を誤認させる表示
健康食品の広告表示の規制に関しては、通常、売買では売主がいわゆるセールストークを行いますので、ある程度の誇張表現が利用されることは規制の対象としておりません。
その一方で、健康増進法第65条第1項においては、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示を行うことについては規制対象としております。
そのため、具体的に何が規制の対象となる「著しく」に該当するかの判断基準が重要となりますが、消費者庁の公表資料では、例えば、一般消費者が、当該健康食品を摂取した場合に実際に得られる真の効果が広告表示に記載されたとおりではないことを知っていれば、その食品に誘引されることは通常ないと判断される場合は、「著しく」に該当する旨が説明されています。
要するに、そのことを知っていれば買わなかったのに知らなかったから買ってしまった、というようなケースであり、刑事上も詐欺行為に該当するようなケースが想定されているようです。しかしながら、ここまではいかずとも、例えば、そのことを知っていれば買ったかどうかわからない(多分買わなかっただろう)、というような微妙な場合にどのように判断すべきかは、個別の事情を踏まえて判断しなければならず、なかなか線引きとしては難しいところです。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。