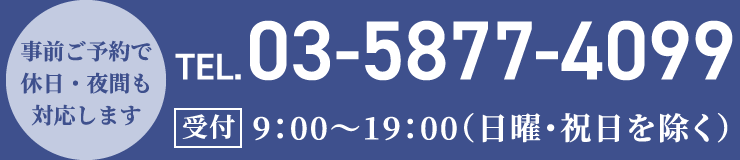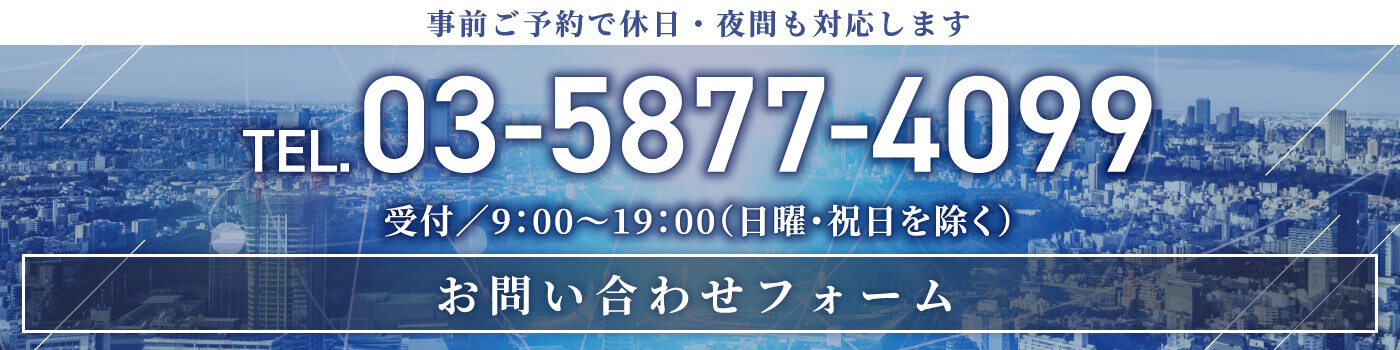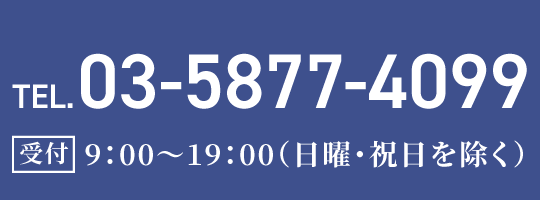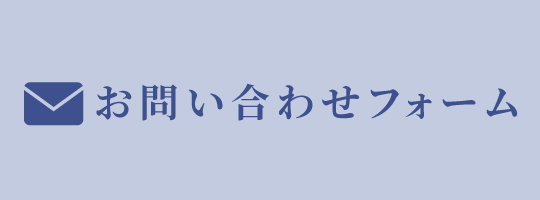「思わずクリックしたくなる短尺動画」「ストーリー仕立ての感動CM」「インフルエンサーのリアルな体験談」
近年、YouTubeやSNSなどで配信される動画広告は、短時間で視覚・聴覚に訴える強力なマーケティングツールとなっています。しかし、動画という媒体の特性上、演出やテンポ感を重視するあまり、実態との乖離が生じやすく、景品表示法の誤認表示リスクが潜んでいます。
今回は、動画広告特有の注意点と、法的に問題となる表現の境界線を整理します。
このページの目次
1 映像表現でも「広告は広告」──表示規制の対象に
動画広告であっても、文字や画像と同様に景品表示法の規制対象です。特に、以下のような動画構成は注意が必要です。
①前半にインパクト重視の過剰表現を配置し、後半で小さく条件を表示する
②ドラマ仕立てで“あくまで演出”と見せつつ、事実と誤認されるような効果描写を含む
③セリフ・ナレーションで保証や絶対性をうたう表現(例:「これを使えば絶対に改善!」)
広告である限り、“演出だから”では許されません。 消費者がその映像から受ける印象が、実際のサービス内容と食い違う場合、それは「優良誤認表示」とみなされるおそれがあります。
2 ビフォーアフター・実演シーンはとくに注意
動画広告では、「実際に使ってみた」「使ったらこんなに変わった」などの体験型演出や比較演出が非常に多く用いられます。 しかし、それが事実無根の演出や加工である場合、処分対象になり得ます。
よくあるNG例としては、
①実演シーンで、他社製品をあえて不利に扱う(例:音が鳴らないようスピーカーを切る)
②視覚的効果で大幅に変化したように見せるが、映像加工や撮影条件の違いで演出しているだけ
③実在しないユーザーや専門家による推薦・出演
→ これらは、視覚的印象に基づく誤認表示とされ、行政処分に至った事例もあります。
3 誇張表現・再現性のない事例の扱い
①「たった1日でこんなに変わるなんて!」
②「誰でもできる簡単副業で月収50万円」
③「続けるだけで自然に痩せました!」
これらの表現は、個別の体験談であっても、あたかも一般的効果があるかのように見える構成になっている場合、景表法に抵触する可能性が高くなります。
特に動画では、音楽・テンポ・感情的な演出により消費者の印象を大きく左右するため、誇張や曖昧表現には注意が必要です。
動画広告は、もっとも感情に訴える力を持つ広告手法です。そのぶん、消費者を誤認させない「誠実な演出」への責任も大きいということを忘れてはなりません。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。