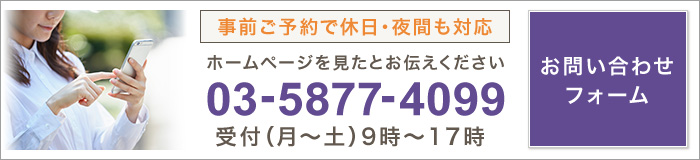インターネット上では、軽い気持ちで投稿・コメントを行った結果、それが「誹謗中傷」と評価され、加害者として責任を問われるケースが増えています。名誉毀損やプライバシー侵害に該当すれば、被害者から損害賠償や刑事告訴を受ける可能性もあり、個人であっても決して免責されません。本記事では、誹謗中傷の加害者側となった場合の法的責任と、取るべき対応について解説いたします。
このページの目次
1 誹謗中傷とは?
誹謗中傷とは、他人を悪く言ったり、社会的評価を下げたりする表現行為をいいますが、特に次のような発言が問題となります。
①「○○は犯罪者」「詐欺会社だ」などの根拠なき断定
②「バカ」「死ね」などの侮辱的な言葉
③セクシャルハラスメント的なコメントや人種・性別に関する差別的表現
④外見や障害を揶揄するような投稿
たとえ事実であっても、公共性や公益性がなく、表現が過剰であれば違法とされる可能性があります。
2 加害者が負う法的責任
①民事責任(損害賠償)
名誉毀損(民法710条)やプライバシー侵害によって、慰謝料・弁護士費用等の損害賠償を請求されることがあります。金額は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
②刑事責任
刑法上は、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(231条)などが成立する可能性があります。被害者の告訴により、警察の捜査や検察による起訴がなされることもあります。
③仮処分や投稿削除の義務
③裁判所の仮処分命令により、当該投稿の削除や再投稿の禁止が命じられることもあります。
3 実例:SNS投稿者に対する損害賠償命令
ある裁判例では、Twitter上で芸能人に対し「整形モンスター」「性格が終わってる」などと繰り返し投稿したユーザーに対し、名誉毀損が認定され、110万円の損害賠償が命じられました。被告は「表現の自由」を主張しましたが、裁判所は「社会的相当性を欠く侮辱的表現」として違法性を認定しました。
4 誹謗中傷してしまった場合の対応
①投稿の削除・謝罪
問題となる投稿に気づいたら、速やかに削除することが重要です。任意の謝罪や、被害者との直接連絡を検討する余地もあります。
②被害者との示談交渉
損害賠償請求や刑事告訴を防ぐため、謝罪文や一定の解決金を支払う形で示談を図ることが可能です。
③弁護士への相談
対応を誤ると、損害が拡大したり法的責任が重くなる可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を検討しましょう。
④匿名でも責任は免れないことを自覚する
匿名での投稿であっても、発信者情報開示請求を通じて身元が特定される可能性があります。過去の投稿が問題視されるケースもあるため、履歴の見直しも重要です。
インターネットは感情的になりやすく、「つい言い過ぎた」ということが誹謗中傷につながるリスクを孕んでいます。重要なのは、発信には責任が伴うという意識を持つことです。
仮に誹謗中傷の加害者となってしまった場合も、誠実に謝罪し、早期に被害回復に努めることで、被害拡大や訴訟リスクを軽減できる場合があります。ご自身の立場に不安を感じたら、迷わず弁護士にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。