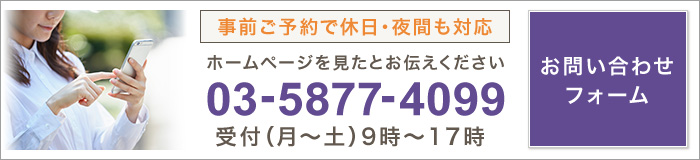インターネット上では、ある人物の名前や住所、勤務先、顔写真などの個人情報を暴露する「特定行為(いわゆる“晒し”)」が頻繁に見られます。一見、正義感から行われることもありますが、特定行為は重大な法的問題を引き起こす行為であり、加害者側が刑事・民事の責任を負う可能性もあります。本記事では、ネット上の“特定”に関する法的リスクを解説いたします。
このページの目次
1 “特定”とは何か
「特定」とは、SNSや掲示板等において、ある人物について以下のような情報を晒す行為を指します。
①氏名、住所、電話番号
②学校名、勤務先
③顔写真や家族構成
④車両ナンバー、通勤経路、SNSアカウントなど
これらの情報が、本人の許可なく公開され、ネット上に拡散されることで、被害者はプライバシーの侵害や嫌がらせ、就業・就学上の支障など深刻な被害を受けることになります。
2 プライバシー権侵害と名誉毀損
特定行為は、以下のような法的責任を生じ得ます。
①プライバシーの侵害(民法709条)
私生活上の事実を無断で公表することは、不法行為に該当します。
②名誉毀損(刑法230条・民法710条)
個人情報の開示によって、社会的評価を下げる結果になれば、名誉毀損と評価されることもあります。
③業務妨害罪・信用毀損罪(刑法233条~234条)
勤務先を晒すことで、企業に対するクレームや迷惑行為が生じた場合、刑事責任が問われる可能性もあります。
3 裁判例:勤務先の晒しによる損害賠償命令
ある裁判例では、ある女性がSNSでの発言をきっかけに炎上し、住所や勤務先を晒された事案について、裁判所は「プライバシー侵害にあたり違法」と認定。投稿者に対して約100万円の損害賠償が命じられました。
この裁判例は、ネット上の“特定”行為が違法であることを明確に示したものです。
4 被害を受けた場合の対応策
①証拠の確保
個人情報が公開された投稿やページのスクリーンショット、URL、投稿日時などを保存します。証拠が削除されても、キャッシュや保存データがあれば対応可能なこともあります。
②削除請求・仮処分
プラットフォーム運営者に対し、プライバシー権侵害や名誉毀損を理由に削除を申し立てます。緊急性が高い場合は、仮処分による対応も視野に入ります。
③発信者情報開示請求と損害賠償請求
加害者が匿名であっても、法的手段によって投稿者の特定を進めることが可能です。損害賠償のほか、再発防止措置や謝罪を求めることもできます。
④警察への相談
晒されたことによってストーカー行為や脅迫を受けるなど、安全上の懸念がある場合は、迷わず警察に相談すべきです。
ネット上での“特定”行為は、たとえ「事実」を投稿していても違法となるケースがあります。情報の公開には常に慎重さが求められます。
被害を受けた際には、被害が拡大する前に速やかに弁護士へ相談し、削除・損害賠償・投稿者特定などの対応を講じることが極めて重要です。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。