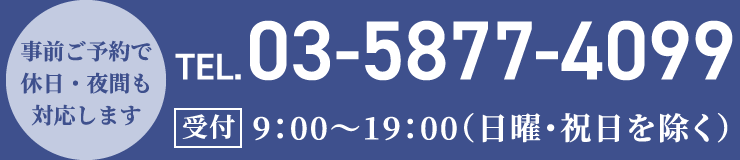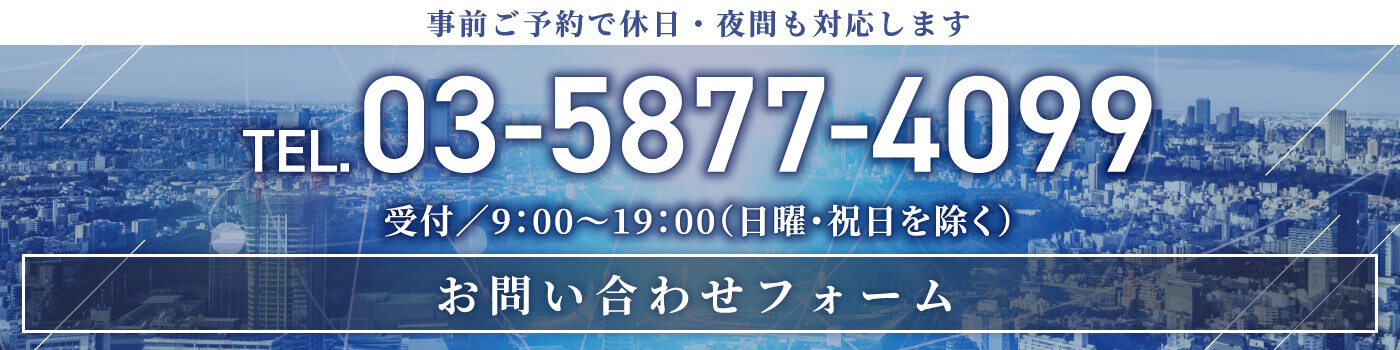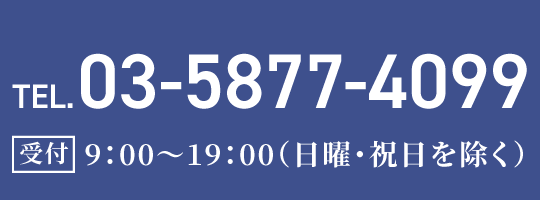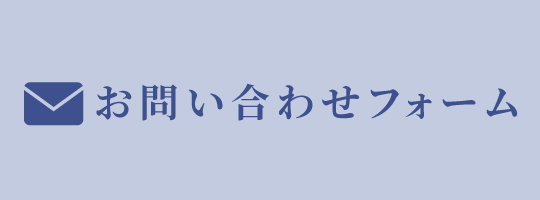「通常価格9,800円 → 今だけ3,980円!」「定価から50%OFF」「期間限定セール実施中」
こうした割引表示は、購買意欲を刺激する広告表現として非常に有効です。しかし、実態に即していない“割引の演出”は、景品表示法上の「有利誤認表示」として違法とされるリスクがあるため、十分な注意が必要です。
このページの目次
1 景品表示法における「有利誤認表示」とは?
有利誤認表示とは、「実際よりも取引条件(価格・サービス内容など)が著しく有利であると誤認させる表示」のことです。割引・セール表示はまさにその代表例であり、“元の価格”が存在しない、または形式的なものであった場合、違法となる可能性が高くなります。
2 NG例:こんな割引表示はリスク大
①「通常価格」として表示している価格が、過去に実際に販売されていなかった
②常に「タイムセール」「期間限定割引」を表示しており、“限定感”が実態と異なる
③ほとんどの顧客が特典を受けられない条件付き価格を、目立つ場所に表示している
④「半額!」と表示しているが、元値が自社で自由に設定された価格(定価ではない)
こうした表示は、実際には消費者に有利でないにもかかわらず、有利に見せることで購買意欲を煽っており、不当表示として措置命令や課徴金納付命令の対象となる可能性があります。
3 「通常価格」には客観的根拠が必要
割引表示の適法性の鍵となるのは、「通常価格」に相当する金額が実際に販売された価格であるかどうかです。具体的には、
①一定期間(目安:過去2週間以上)
②相当な数量・件数(特定の1~2件ではNG)
③継続的に販売されていた価格
これらを満たしていなければ、「通常価格」と表示することはできません。たとえば、一度も9,800円で販売されていない商品に「通常価格9,800円→特価3,980円」と表示するのは違法です。
4 「セール期間」「割引条件」の表示は明確に
割引表示が適法であっても、その適用期間や条件を小さく、あるいは曖昧に表示することで消費者に誤認を与える表現もNGです。
たとえば、
①「期間限定」としながら、実際には常時割引状態
②「会員限定割引」を全体広告で大きく表示し、会員条件を目立たない場所に記載
③「残り〇個!」と表示して在庫を少なく見せる演出が常態化している
これらは、景表法の“実態に即した表示義務”に反する可能性があります。
割引やセール表示は、誠実に運用すれば売上向上に大きく寄与する表現です。しかし、一時的な集客効果を狙って“誇張された価格訴求”を行うと、企業全体の信頼性が損なわれ、法的リスクも大きくなるおそれがあります。
“本当の値引き”こそが、消費者の信頼とリピートにつながることを意識して、表現を設計することが重要です。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。