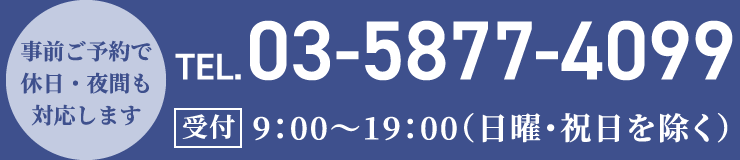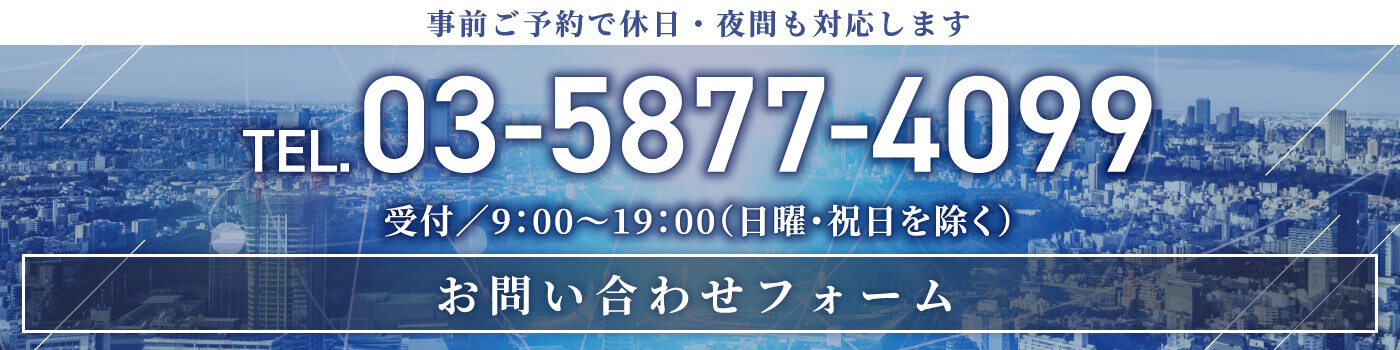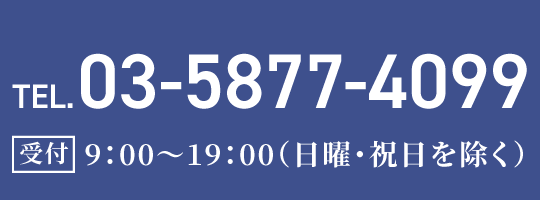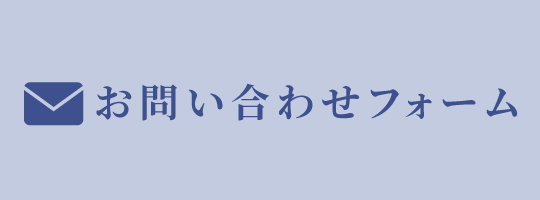出版・メディア業界では、新刊書籍・雑誌・電子書籍などの販売促進のために、帯コメント・ランキング表示・書評の抜粋などを活用した広告が広く用いられています。
表現の自由度が高く、感性や印象に訴える手法が多い一方で、事実に基づかない実績表示や誤解を与える引用表現は、景品表示法などの法的規制の対象となることがあります。
このページの目次
1 ランキング表示のリスク
書籍広告では、「◯◯書店ランキング第1位」「Amazonでベストセラー1位獲得」といった表示がよく使われます。消費者にとって“売れている”印象を与える有力な訴求ですが、実態と異なる場合や根拠が不明確な場合には、優良誤認表示に該当するおそれがあります。
注意が必要なケースとしては、
①一時的なランキング1位(例:深夜帯のみ)を恒常的な実績であるかのように表示
②ランキングの対象期間・部門・販売形式(紙/電子)などが不明確
③調査元(書店/ECサイト)を記載せず「ランキング1位」とのみ記載
ランキングを表示する際は、必ず以下の情報を明確に表示する必要があります。
①調査対象(例:◯月◯日~◯月◯日の売上)
②調査主体(例:Amazon/楽天/特定書店チェーン)
③ランキングの部門(文芸、ビジネス、電子書籍など)
2 書評の抜粋・帯コメントの注意点
「涙が止まらなかった」「全ビジネスパーソン必読」「◯◯先生大絶賛」など、書評や推薦コメントを広告に使うことは一般的ですが、その出典や文脈を正確に伝えない場合、消費者を誤認させる表示として問題になる可能性があります。
よくあるリスク例としては、
①実際には“やや好意的”程度の評価を、極めて高評価であるかのように引用する
②コメントの一部を切り取り、本来の文脈と異なる印象を与える
③芸能人・著名人のコメントを掲載するが、本人から承諾を得ていない
③AI書評や一般ユーザーのレビューを、第三者の評価として誤認させる
引用する場合は、出典(媒体名・発行日など)を明記し、文脈を変えずに使用することが原則です。また、許諾を得たコメントであるかどうかも、使用前に必ず確認すべきです。
3 キャッチコピー・誇張表現の扱い
「今年一番泣ける恋愛小説」「10年に一度の衝撃作」など、印象的なキャッチコピーも多く見られます。これらは読者の主観に委ねられる“感想的表現”として認められるケースもありますが、特定の実績(売上・評価)や事実と結びつける場合は、根拠が求められます。
例:「書店員が選ぶ1位の小説」→ 実際にそうしたランキングが存在しているか、確認・表示が必要。
4 出版広告のチェックポイントまとめ
①ランキング表示には、調査主体・対象期間・部門の明示があるか
②書評の引用は、出典・文脈・許諾の有無を確認しているか
③芸能人や著名人の推薦コメントは、本人からの承諾があるか
④感性的キャッチコピーでも、事実に基づく表現か否かを区別して使い分ける
⑤SNS・電子広告では、広告であることの明示(ステマ対策)が行われているか
出版・メディア業界では、読者の感情に訴える「言葉の力」が広告の要となりますが、だからこそ「信頼性」と「根拠」が伴ってこそ、本当に響く広告になります。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。