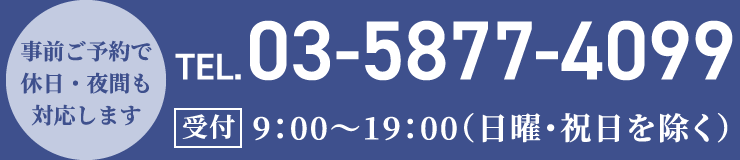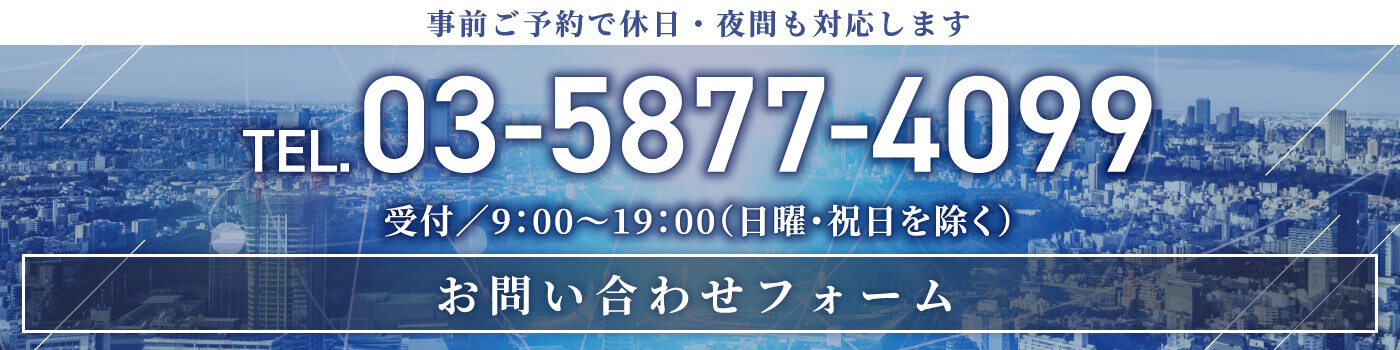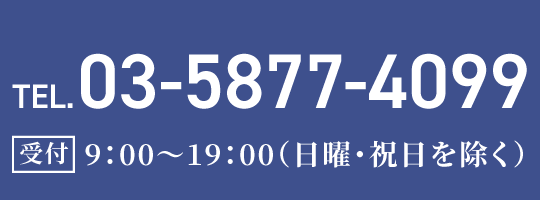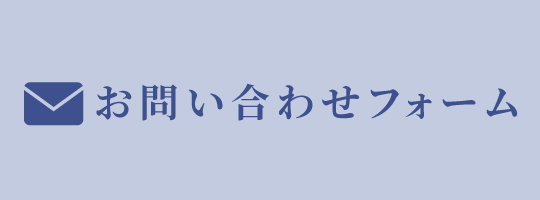「#使ってみた」「大好きな商品です!」「これはガチでおすすめ!」
インフルエンサーや一般ユーザーが投稿する、自然体な“レビュー風”コンテンツは消費者に強く響きます。ですが、企業が報酬や商品提供をしていたにもかかわらず、それを明示しない場合、景品表示法上の「不当表示」(いわゆるステマ)に該当する可能性があります。
2023年10月からは、消費者庁によるステルスマーケティング規制が明文化され、罰則付きの法規制の対象となりました。本稿ではそのポイントをわかりやすく解説します。
このページの目次
1 そもそも「ステルスマーケティング」とは?
ステルスマーケティング(ステマ)とは、「広告・PRであるにもかかわらず、それを隠して宣伝する手法」のことです。
たとえば以下のようなケースが該当します。
①インフルエンサーに報酬を支払っているが、「広告」「PR」と明示せず投稿させる
②モニターや関係者の投稿を、一般ユーザーの感想のように見せる
③企業が自らアカウントを作成し、第三者のふりをして投稿を行う(自作自演)
こうした行為は、消費者にとって「第三者の公平な感想」だと誤認させるため、表示内容がたとえ事実であっても、不当表示として違法となるおそれがあります。
2 2023年景品表示法改正のポイント
ステマ規制が明文化されたことで、以下のような基準が明確になりました。
①事業者の表示であることが消費者にとって明瞭でない場合 → 不当表示とみなされる
②消費者に「事業者が関与している」と分かるように明示しなければならない
③違反すれば、措置命令・課徴金・指導の対象になる
つまり、「広告」「PR」「タイアップ」「提供」などの表示が投稿の目立つ位置に必要であり、単にハッシュタグで一つ添えるだけでは不十分な場合もあるということです。
3 インフルエンサー・PR投稿での実務対応ポイント
インフルエンサーを起用した広告活動では、以下のような対応が求められます。
①表示ルールの共有
投稿前に「#PR」「#広告」「提供:企業名」など、明確な表示ルールを契約・指示する
②表示位置に配慮
ハッシュタグの後半に埋もれていたり、画像や動画の本文内に埋もれている場合、表示が明瞭とは認められない可能性あり
③内容監修の透明性
企業が投稿内容に編集・監修を加えている場合は、広告主責任が発生するため、内容にも適法性を持たせる必要あり
④記録保存
報酬の提供内容・時期・投稿原稿などの記録を保存しておくことも、万一の行政対応や問い合わせ時の対応に役立ちます。
ステマは一度発覚すると、法的リスク以上に「企業への信頼喪失」という大きな代償を招きます。
広告であることを“隠さない”どころか、誠実に明示することで、むしろ消費者の共感を得られる時代です。
インフルエンサー起用においても、正しい表示と責任ある情報発信を徹底することが、長期的なブランド価値につながります。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。