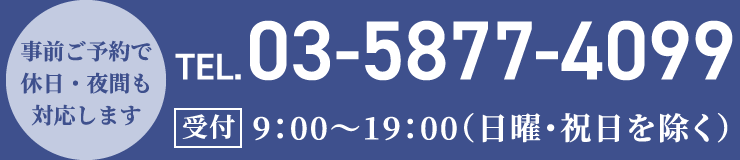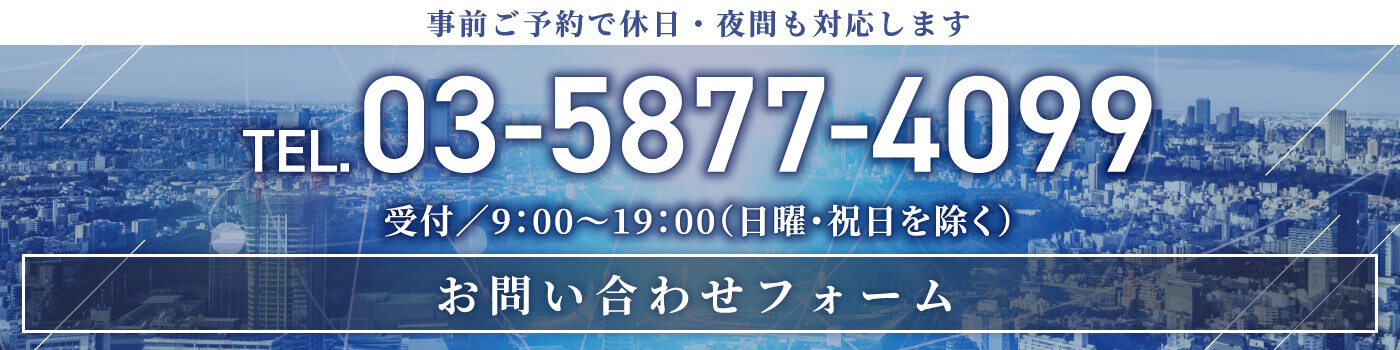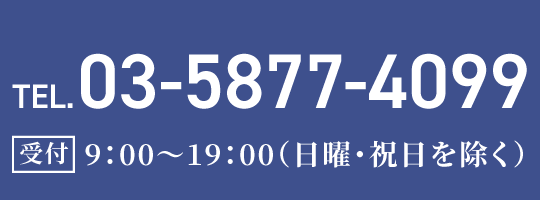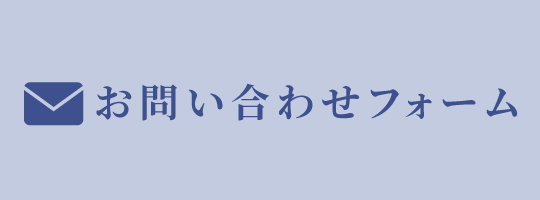Archive for the ‘広告関連法務’ Category
ペット・動物関連業界の広告と法的リスク
ペットフード、動物病院、トリミングサロン、ブリーダー販売、ペット保険など、ペット関連市場は近年拡大を続けており、広告展開も多様化しています。しかし、動物を取り扱うこの業界では、誤認を招く健康効果の表示や、希少性の強調、販売方法の不適切な表現が問題となりやすく、景品表示法、動物愛護法、健康増進法などの複数の法規制に注意が必要です。
1 ペットフード・サプリの「健康効果表示」は特に注意
近年、犬猫向けの健康食品やサプリメント、機能性フードが注目されていますが、「関節が強くなる」「毛並みがツヤツヤに」「涙やけが改善」などの効果表示は、人間向けの健康食品と同様に、裏付けのない表示は景品表示法違反となる可能性があります。
また、「医師監修」「動物病院推奨」などの表現も、監修・推奨の事実や内容が明確でない場合には誤認表示とみなされます。
特に注意が必要な点としては、
①「老犬にもおすすめ!関節がよく動くように!」→ 効能効果の科学的根拠が必要
②「獣医師が開発」→ 実際には名義貸しである場合、優良誤認のおそれ
③「○○成分で長生きサポート」→ 長寿との因果関係が不明瞭であれば不当表示
ヒト用サプリメント同様、「機能性表示食品」等の制度はペットには適用されません。そのため、より慎重な表現運用が必要です。
2 ペットの販売における「希少性」「人気」「血統」表示のリスク
ペットショップやブリーダーサイトなどでは、「希少犬種」「血統書付き」「TVで話題の人気猫種」などの表現が多く見られますが、これらも根拠が不明確な場合、景表法違反のリスクがあります。
以下のような表示は特に注意が必要です。
①「国内に数頭のみ」→ 出典・調査基準が不明
②「チャンピオン犬の子」→ 実際の血統証明が確認できない
③「人気No.1猫種」→ ランキングや根拠を明示していない
また、動物の販売にあたっては、動物愛護法に基づく表示義務(販売業者情報、生年月日、親の情報など)があり、それらが広告上に適切に記載されていない場合、行政処分や業務停止命令の対象になることもあります。
3 トリミングやペットホテルの「安心・安全」表示にも根拠を
「24時間スタッフ常駐」「動物看護師が常勤」「安心・安全な施設」といった表現も多く見られますが、実際には一時的な対応や外部委託である場合、消費者に誤認を与える表現とされるリスクがあります。
また、「○○検定取得」「認定サロン」などの資格表示も、実在する団体の認証か、一般社団法人を名乗る私的団体による自称資格なのかで、信頼性に大きな差があります。
4 チェックポイントまとめ
ペット業界の広告で確認すべきポイントは次のとおりです。
①健康効果を示唆する表現に明確なエビデンス(試験データなど)があるか
②医師・専門家・団体名の表示に承諾・実態の裏付けがあるか
③「希少種」「血統」などの表示に公的証明や第三者による確認があるか
④表示義務事項(動物愛護法の販売情報等)を広告上に適切に掲載しているか
⑤サービスの安心・安全表示に客観的裏付けや条件明示があるか
ペットは“家族の一員”であり、その広告が不誠実であれば、消費者の感情的反発や信用失墜を招きかねません。だからこそ、動物への思いやりと法令遵守を両立させた広告表現が、信頼される企業の証しとなります。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
出版・メディア業界の広告と法的留意点
出版・メディア業界では、新刊書籍・雑誌・電子書籍などの販売促進のために、帯コメント・ランキング表示・書評の抜粋などを活用した広告が広く用いられています。
表現の自由度が高く、感性や印象に訴える手法が多い一方で、事実に基づかない実績表示や誤解を与える引用表現は、景品表示法などの法的規制の対象となることがあります。
1 ランキング表示のリスク
書籍広告では、「◯◯書店ランキング第1位」「Amazonでベストセラー1位獲得」といった表示がよく使われます。消費者にとって“売れている”印象を与える有力な訴求ですが、実態と異なる場合や根拠が不明確な場合には、優良誤認表示に該当するおそれがあります。
注意が必要なケースとしては、
①一時的なランキング1位(例:深夜帯のみ)を恒常的な実績であるかのように表示
②ランキングの対象期間・部門・販売形式(紙/電子)などが不明確
③調査元(書店/ECサイト)を記載せず「ランキング1位」とのみ記載
ランキングを表示する際は、必ず以下の情報を明確に表示する必要があります。
①調査対象(例:◯月◯日~◯月◯日の売上)
②調査主体(例:Amazon/楽天/特定書店チェーン)
③ランキングの部門(文芸、ビジネス、電子書籍など)
2 書評の抜粋・帯コメントの注意点
「涙が止まらなかった」「全ビジネスパーソン必読」「◯◯先生大絶賛」など、書評や推薦コメントを広告に使うことは一般的ですが、その出典や文脈を正確に伝えない場合、消費者を誤認させる表示として問題になる可能性があります。
よくあるリスク例としては、
①実際には“やや好意的”程度の評価を、極めて高評価であるかのように引用する
②コメントの一部を切り取り、本来の文脈と異なる印象を与える
③芸能人・著名人のコメントを掲載するが、本人から承諾を得ていない
③AI書評や一般ユーザーのレビューを、第三者の評価として誤認させる
引用する場合は、出典(媒体名・発行日など)を明記し、文脈を変えずに使用することが原則です。また、許諾を得たコメントであるかどうかも、使用前に必ず確認すべきです。
3 キャッチコピー・誇張表現の扱い
「今年一番泣ける恋愛小説」「10年に一度の衝撃作」など、印象的なキャッチコピーも多く見られます。これらは読者の主観に委ねられる“感想的表現”として認められるケースもありますが、特定の実績(売上・評価)や事実と結びつける場合は、根拠が求められます。
例:「書店員が選ぶ1位の小説」→ 実際にそうしたランキングが存在しているか、確認・表示が必要。
4 出版広告のチェックポイントまとめ
①ランキング表示には、調査主体・対象期間・部門の明示があるか
②書評の引用は、出典・文脈・許諾の有無を確認しているか
③芸能人や著名人の推薦コメントは、本人からの承諾があるか
④感性的キャッチコピーでも、事実に基づく表現か否かを区別して使い分ける
⑤SNS・電子広告では、広告であることの明示(ステマ対策)が行われているか
出版・メディア業界では、読者の感情に訴える「言葉の力」が広告の要となりますが、だからこそ「信頼性」と「根拠」が伴ってこそ、本当に響く広告になります。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
旅行・観光業界の広告と法的リスク
旅行代理店、宿泊施設、ツアー企画会社、観光PR事業者など、旅行・観光業界では「非日常」や「感動」をテーマにした広告が多く見られます。SNSや動画を活用した訴求が盛んであり、消費者の期待も高い分野ですが、その一方で、実態との乖離がある表現や誤認を招く価格表示は、景品表示法違反などの法的リスクを招く可能性があります。
1 優良誤認表示の典型例:「体験談」「絶景」「ラグジュアリー」
観光業界では、視覚的な訴求力が重視され、「実際よりも良く見せたい」という誘惑に駆られがちです。ですが、過度に誇張された写真やキャッチコピーは、優良誤認表示に該当するおそれがあります。
たとえば以下のような表現には注意が必要です。
①加工した写真を使用し、実際の宿泊施設や景色と著しく異なる印象を与える
②期間限定の特別仕様(例:特別装飾や演出)を通年実施のように表示する
③「お客様満足度98%」「最高の思い出になりました!」といった体験談を広告に掲載しているが、裏付けとなるアンケート調査や実在性の確認がない
旅行広告では、感動を演出する体験談やレビューが多用されますが、これらが事実でなかったり、過度に一般化された「お客様の声」である場合は、消費者に誤認を与えるリスクがあります。
2 有利誤認表示の典型例:料金・キャンペーン表示
「〇月限定!今だけ30%OFF!」「3泊4日航空券・ホテル込みで29,800円!」など、価格訴求は非常に効果的ですが、実際の料金条件や適用範囲が小さく明記されているだけの場合、有利誤認表示に該当する可能性があります。
以下のようなケースが典型例です。
①「29,800円~」と表示しつつ、実際にはほとんどの日程でその価格のプランが存在しない
②表示価格に含まれない費用(例:空港税、入湯税、施設使用料など)が多く、総額との乖離がある
③「無料送迎」「朝食付き」と表示しているが、予約条件付き(例:◯泊以上)であることを目立たない場所に記載
旅行業界では、価格が決め手になることが多いため、価格表示は特に厳格な審査を経て表記する必要があります。
3 リーガルチェックのポイント
旅行業界では、景品表示法だけでなく、旅行業法・消費者契約法の適用もあります。広告における「取消料」や「キャンセルポリシー」などの表示内容が明確でないと、不当条項や情報不足による契約トラブルに発展することもあります。
チェックすべき主なポイントは以下のとおりです。
①写真や動画は実際の風景・施設と著しい乖離がないか
②「体験談」「レビュー」は実在する利用者の声かつ脚色されていないか
③表示価格に含まれる内容・除外される費用を明確に示しているか
④キャンペーンや特典表示は適用条件を大きくわかりやすく記載しているか
⑤キャンセル料・変更手数料などの条件が誤認なく説明されているか
旅行・観光業界の広告は、夢や非日常を売る仕事だからこそ、事実に即した誠実な情報提供が求められます。誤解を招かない、正確で信頼ある広告こそが、「また利用したい」というリピーターを生み、長期的なブランド価値に繋がるのです。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
アパレル・ファッション業界の広告と法的リスク
アパレル・ファッション業界では、季節ごとの新作プロモーション、SNSを活用した販促、ECサイトでのセール表示など、多彩な広告展開が行われています。デザイン性や感性を訴求する業界である一方、表示に法的な裏付けがない場合、景品表示法や家庭用品品質表示法等の法令に抵触するリスクがあるため、注意が必要です。
本業界で特に問題となりやすいのが、以下の3つの表示です。
①素材や原産国に関する表示
②価格(割引)表示
③機能性(防水・UVカットなど)の表示
1 素材表示と原産国表示の注意点
アパレル製品の品質表示には、「家庭用品品質表示法」が適用され、素材(繊維の組成)、洗濯表示、原産国などの正確な表示が求められます。たとえば、以下のような表示は問題になります。
①実際にはポリエステル混紡であるにもかかわらず「100%コットン」と記載
②中国製である商品に「Made in Japan」と表示
③特定の高級素材(例:カシミヤ)を一部しか使用していないのに、製品全体がその素材であるかのような表記
これらは景表法の優良誤認表示、品質表示法違反の両方に該当する可能性があります。
2 セール・割引表示の落とし穴
ECサイトや店頭ポスターで頻繁に見かける「通常価格から○%オフ」「今だけタイムセール」といった表示にも、法的リスクが潜んでいます。
景表法上、「通常価格」とは、過去に相当期間実際に販売された価格でなければならず、存在しない価格を“定価”として大幅割引を訴求すると、有利誤認表示として違法となるおそれがあります。
①常に「タイムセール」「ラスト1点」と表示している
②「通常9,800円→今だけ3,980円!」だが、実際に9,800円で販売された期間が極端に短い
③セール価格を継続的に使用しており、実質的に通常価格となっている
これらは、過去に消費者庁からの措置命令が出された事例もあります。
3 機能性表示・ナンバーワン表示
「UVカット90%」「防水加工済」「業界No.1のリピート率」など、機能性や実績を訴求する表現も人気ですが、これらの表示には合理的根拠資料が必要です。
特に「No.1」「人気ランキング1位」などの表現は、出典・調査機関・時期・調査方法の明示が不可欠です。根拠が不明確な場合、優良誤認表示として規制の対象になります。
4 チェックポイント
アパレル広告でリーガルチェックすべきポイントは以下のとおりです。
①素材や原産国の表示は、実際の商品と完全に一致しているか
②セールや割引価格に使用している「通常価格」は過去に実績があるか
③「限定」「ラスト1点」「人気」などの煽り表現は、実態に即しているか
④機能性表示には、第三者試験・社内試験などの根拠資料があるか
⑤ランキング・No.1表示の際は、出典・条件を明示しているか
アパレル業界では“感性に訴える表現”が中心になりがちですが、だからこそ信頼性ある表示とのバランスが求められます。ファッションの価値は、素材・デザインと同様に、“誠実な伝え方”にも宿ります。
次回は、「旅行・観光業界における広告と『体験談』『価格表示』の法的注意点」を解説いたします。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
IT・SaaS業界の広告と法的リスク
クラウドサービス、業務システム、アプリケーションなど、IT・SaaS業界の広告は、デジタル領域の拡大とともにますます活発化しています。導入実績や機能の優位性、コスト削減効果など、企業の経営層や担当者の目を引くような訴求がなされる一方で、根拠のない実績表示や誤解を招く機能比較などは、景品表示法違反につながるリスクがあるため注意が必要です。
1 主とした法規制
IT・SaaS業界で広告に関わる主な法律は、以下のとおりです。
①景品表示法(優良誤認・有利誤認表示)
②不正競争防止法(誤認惹起表示・営業秘密の不正使用)
③特定商取引法(BtoC向けの継続課金型サービスなど)
2 リスクのある広告表現
たとえば、次のような広告表現はリスクがあります。
①「導入社数10,000社突破!」→ 実際は無料トライアル登録を含む数字で、有償契約数ではない
②「業界No.1」「国内シェア1位」→ 出典不明、調査主体・調査方法が非公開
③「年間100時間の業務削減に成功!」→ 自社ユーザー1社の事例であり、一般的な効果ではない
④「競合より安く、高機能」→ 他社製品の機能比較が客観的でなく、根拠の提示がない
これらはいずれも、優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性がある広告例です。SaaSの特性上、サービスの実体が目に見えないため、広告上の表現がユーザーの判断材料のほとんどを占めることになります。そのため、表現の裏付けとなる合理的根拠資料(エビデンス)を準備し、開示できる状態にしておくことが重要です。
さらに、よくあるトラブルとして、利用規約に記載された条件と広告表示の齟齬があります。たとえば「いつでも解約可能」と広告で訴求しているにもかかわらず、実際は年間契約のみ、途中解約は不可とされている場合、消費者から「詐欺的」と批判されるだけでなく、景表法違反または特商法違反の対象になる可能性があります。
3 リーガルチェックのポイント
SaaS業界における広告のチェックポイントは、以下のとおりです。
①実績表示(導入数、満足度、業界シェア等)は出典・調査方法・調査時期を明示しているか
②利用条件(価格、機能制限、解約条件など)は、広告上で正確かつ明確に表示されているか
③比較広告を行う場合、客観性と公平性が確保されているか
④他社名・ロゴを無断使用していないか(著作権・不正競争防止法への配慮)
⑤ユーザーの声・体験談が実在するものかつ脚色されていないか
また、最近ではYouTubeやオウンドメディア、比較サイトを使ったマーケティングも盛んですが、それらが広告であるにもかかわらず「中立レビュー」を装っている場合、ステマ規制の対象となる可能性もあります。
IT・SaaS業界では、製品そのものの“見た目”で差別化することが難しいからこそ、「広告で信頼を築く」姿勢が、契約継続や評判維持に直結します。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
飲食・外食業界の広告と法的リスク
レストラン、カフェ、ファストフードチェーン、デリバリーサービス、食品メーカーなど、飲食・外食業界では、日々さまざまな広告が展開されています。SNSや動画広告、ポスターなど多彩な媒体で魅力的に訴求される一方で、食品に関する表示には厳格なルールが課されており、違反すると行政処分や社会的信用の低下を招くリスクがあります。
1 飲食業界における広告規制
まず、飲食業界における広告で注意すべき主要な法令は、以下の3つです。
①景品表示法(景表法)
②食品表示法
③健康増進法(特定保健用食品等)
2 景表法上の規制
特に景表法では、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」が禁止されており、実際より著しく優れている、有利であると誤認される表現を使うと違法になります。
たとえば、以下のような表現が問題となる可能性があります。
①「無添加」「オーガニック」「国産100%」などの表示に根拠がない
②「他店の倍の量!」などの比較広告に客観的裏付けがない
③「今だけ半額」などの価格表示に、実際は“常時キャンペーン状態”で通常価格が存在しないケース
こうした表現は、根拠資料がない場合や表示が曖昧な場合に措置命令・課徴金納付命令の対象となることがあります。
2 食品表示法上の規制
次に、食品表示法にも注意が必要です。この法律は、原材料名、栄養成分、アレルゲン表示、消費期限などについて詳細に定められています。
たとえば、以下のような誤表示は法令違反です。
①実際には使用していない食材を「使用」と表示する(例:「北海道産バター使用」)
②加工食品において、加熱処理の有無を誤認させる表示をする(例:「生ハム風」なのに“生”と誤認させる)
③内容量をごまかす(例:「お肉たっぷり」と書かれているが、実際には少量しか使用していない)
また、健康訴求(ヘルスクレーム)に関する表現は、健康増進法の規制対象となります。「○○を食べると痩せる」「血圧が下がる」といった表示は、特定保健用食品や機能性表示食品でなければ使うことができません。
一般の食品でこのような表現を行うと、違法表示と判断されます。
3 リーガルチェックのポイント
飲食業界の広告でリーガルチェックすべきポイントは以下の通りです。
①「無添加」「国産」などの表示に根拠資料はあるか(証明可能か)
②価格表示は実態と合致しているか、キャンペーンは一時的なものか
③栄養成分や原材料の表記に誤りや誇張はないか
④健康効果を示唆する表現は、法的に許容される商品かどうか
⑤ビジュアルと実物の乖離が著しくないか(例:写真と実物のサイズ・量の差)
飲食業界では、広告が「美味しそう」「安心できそう」といった印象を左右します。しかし、印象操作に頼りすぎた表現は、違法リスクとブランド毀損の二重のリスクを招きかねません。
法令に則った誠実な広告こそが、「また食べたい」「信頼できる」という顧客の声につながります。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
医療機関・クリニックにおける広告と法的規制
1 医療広告ガイドラインについて
美容外科、歯科、皮膚科、AGAクリニック、自由診療クリニックなど、医療機関による広告はここ数年で非常に多様化しています。しかし、医療に関する広告には特有の厳格な法規制が存在し、一般的な業種とは異なる広告ルールが適用されます。中でも中心となるのが、医療法および医療広告ガイドラインです。
まず大前提として、医療機関の広告には、原則として掲載できる事項が限定されているという特徴があります。たとえば、広告できるのは以下のような情報に限られています。
①診療科目、診療時間、所在地、医師の氏名
②診療内容の具体的な説明(ただし公正で客観的なものに限る)
③治療実績や設備、費用(一定の条件下で表示可能)
このように、「医療広告は原則禁止、例外的に許可された内容のみ可」というスタンスであることを理解しておくことが重要です。
2 問題となる広告表現
問題となる広告表現には、以下のようなものがあります。
①「絶対に治ります」「100%成功」などの断定的表現
②「痛くない」「1日で治療完了」などの主観的・誇張的表現
③芸能人や有名人の写真を用いた治療結果の例示(体験談含む)
④ビフォーアフター写真の掲載(特定条件下を除き原則不可)
これらの表現は、医療法によって禁止されているか、あるいは「医療広告ガイドライン」により厳しく制限されています。特にビフォーアフター写真や体験談の掲載については、2023年現在でも違反広告の代表例として繰り返し指摘されています。
さらに、自由診療クリニックや美容医療の分野では、景品表示法の「優良誤認表示」に該当する可能性もあります。たとえば、「二重術で理想の目元に!」「10歳若返る美肌治療」など、実際より著しく優れていると誤認させる表現は、医療法と景表法の双方に違反するリスクがあります。
3 リーガルチェックのポイント
医療機関の広告における主なリーガルチェック項目は以下のとおりです。
①医療広告ガイドラインに定められた事項以外の表示をしていないか
②治療の安全性・効果について断定的な表現をしていないか
③ビフォーアフター写真や体験談を無条件に掲載していないか
④根拠のない「安さ」「安心」「人気」などの表示を行っていないか
⑤自由診療の価格は税込・自費であることを明確に表示しているか
なお、医療広告の監視は年々強化されており、都道府県の衛生主管部局や厚労省が指導・勧告を行うケースも増加しています。違反広告が問題視されれば、改善命令、公表、最悪の場合は行政処分に発展する可能性もあります。
医療広告は、患者の健康や命に直接関わる情報であるからこそ、「安心・信頼」の根拠は法令遵守に裏打ちされる必要があるのです。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
金融業界の広告における規制とチェックポイント
金融業界では、ローン・クレジットカード・保険・証券・投資信託・仮想通貨など、幅広い金融商品が広告対象となります。
しかし、これらの広告は法律による規制が非常に多岐にわたり、景品表示法に加え、金融商品取引法、貸金業法、保険業法など複数の法令の適用を受けるため、特に慎重なリーガルチェックが求められます。
1 金商法にはご注意ください
たとえば、投資関連の広告においては、金融商品取引法(いわゆる「金商法」)により、虚偽記載や誤認を招く表示が禁止されています。代表的な問題表現は以下の通りです。
①「元本保証」「絶対儲かる」などの断定的な利益保証
②実際にはリスクの高い商品に「安全・確実」などの表現を用いる
③高騰した実績だけを強調し、過去の暴落やリスクを伏せる表現
④リターン情報だけ記載し、手数料や元本割れリスクを目立たせていない広告
これらはいずれも誤認を生じさせる表示に該当し、金融庁や消費者庁から行政処分・業務改善命令を受ける可能性があります。
2 その他の法規制
また、ローンやクレジットカードの広告では、貸金業法および割賦販売法の規制対象となります。金利・返済期間・手数料などについて正確な表示が義務付けられており、たとえば以下のような表現は問題となります。
①実質年率や遅延損害金などの開示がない
②「無審査」「誰でも借りられる」といった誤解を招く誘引
③初回のみの金利を大きく強調し、2回目以降の条件を小さく表示する
これらは「誇大広告」「不当な誘引」として、違法性が問われる場合があります。特に、資金に困っている消費者に誤解を与える広告は、社会的非難も大きくなります。
さらに、保険商品を取り扱う場合には保険業法が関わってきます。保険に関する広告では、保障内容・免責事項・支払い条件などの重要な情報を適切に表示しなければならず、誤解を招くような表現や比較広告には厳しい制限があります。
近年では、金融系YouTuberやSNSでの投資情報の発信も増えていますが、それらが広告である場合には、「広告であることの明示」および誤認防止の配慮が不可欠です。景表法のステマ規制や金商法による誇大表示の禁止は、個人や企業を問わず適用されます。
3 リーガルチェックの際のチェックポイント
金融業界の広告におけるチェックポイントは以下の通りです。
①利益保証・断定的表現を避ける(例:「確実に儲かる」など)
②リスク・手数料・条件なども平等なバランスで表示する
③金融商品ごとの関連法令(貸金業法・金商法・保険業法など)を確認する
④動画・SNS等の媒体を使う場合でも表示責任は変わらないことを意識する
⑤広告表示と実際の商品説明に齟齬がないよう整合性を保つ
金融広告は、誤認や過剰な誘引があると法的リスクだけでなく、企業の社会的信頼も大きく損なう結果になります。だからこそ、高い透明性と誠実な表現が求められるのです。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告方法でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
教育・スクール業界の広告に潜むリスクと景表法のチェックポイント
学習塾、予備校、通信講座、資格スクール、英会話教室など、教育・スクール業界では、受講者の成績向上や合格実績を訴求する広告が日常的に展開されています。
しかし、こうした広告は、消費者(受講希望者や保護者)の期待値が高い分、表示内容に根拠がなかったり誤認を招く表現を用いると、法的リスクが非常に高くなる分野です。
1 景表法にはご注意ください
教育業界の広告が規制される主な法律は、景品表示法です。特に、「優良誤認表示」に該当するかどうかが焦点になります。
たとえば以下のような表現は、注意が必要です。
①「合格率95%!※当社比」など、算出根拠があいまいな成功実績
②「偏差値30から東大合格」など、実例の誇張や再現性の説明がない表示
③「受講生の8割が年収アップ」などのデータ表示に、出典や調査方法が明記されていないケース
④「日本最大級」「No.1」「絶対合格」など、定義や比較根拠が不明確なスローガン
このような表示は、合理的な根拠資料がない限り、違法とされる可能性が高く、過去にも大手スクール事業者が行政処分を受けた事例があります。
特に「合格率」「成績アップ率」などは、数字で訴求することで説得力が増す一方、その裏付けとなる調査対象・期間・対象者数・条件などが明示されていなければ、景表法違反と判断されるリスクがあるため、非常に慎重な運用が求められます。
2 口コミの利用にもご注意ください
また、「保護者の声」「生徒の体験談」などもよく使われる手法ですが、実在の人物の発言であることを示す根拠が必要です。
架空の感想、あるいは事実と異なる脚色がされている場合は、消費者を誤認させる表示となる可能性があります。
教育業界では、広告内容が未成年者やその保護者に与える影響も大きく、企業としての説明責任と誠実さがより強く求められます。そのため、広告制作の際には、以下のようなチェック体制を整えることが推奨されます。
①合格実績や成績向上に関する表示には、必ずエビデンス(資料)を準備する
②表現の「再現性」や「条件」を明確に記載する(例:「当社模試を複数回受講した生徒に限る」など)
③インタビュー形式や体験談には、実在性と事実性を担保する証拠を保持する
④比較表現やナンバーワン表示は、出典・調査主体・調査時期・方法を明記する
特に競争が激しい都市部では、少しでも差別化を図ろうとするあまり、誇張や不適切な表示に踏み込んでしまうケースも見受けられますが、それは短期的な効果にとどまり、法的リスクやブランド毀損につながる恐れがあります。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートしております。広告法務でお悩みの場合はお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
人材紹介・派遣業界における広告のルールとリーガルチェック
人材紹介・派遣業界では、求職者を惹きつけるために、求人情報や就業先の魅力をアピールする広告が数多く展開されています。ですが、表現の仕方を誤ると、職業安定法・景品表示法・労働者派遣法などの法令に抵触するおそれがあり、他の業種とは異なる慎重さが求められる領域です。
1 求人広告と法規制
まず、求人広告で最も基本となるのが、職業安定法およびその下位法令である「職業紹介事業者指針」、「募集情報等提供事業に関する指針」などの規制です。これらでは、求職者が就業先を選ぶにあたって誤解を招かないよう、正確かつ最新の情報を掲載することが義務付けられています。
たとえば、以下のような広告表現は法的リスクを伴います。
①実際には埋まっている求人を「募集中」と表示し続ける
②月収例に「残業代込み」「インセンティブ込み」の金額のみを掲載し、内訳を明示しない
③「正社員登用率90%」と表示しながら、根拠となるデータがない
④「未経験歓迎」と書かれていても、実際には実務経験が必須
このような表示は、職業安定法違反や景表法の優良誤認表示に該当する可能性があります。特に、給与・雇用条件・勤務地といった『生活に直結する情報』については、誇張やあいまいな表現は避けなければなりません。
また、派遣業界では労働者派遣法にも留意する必要があります。派遣スタッフを募集する際には、派遣先企業名、業務内容、派遣期間、労働条件等の詳細を明示することが求められています。特定の派遣先との関係性や待遇面について、実態と異なる内容を記載した場合、行政指導や許可取消のリスクもあり得ます。
2 リーガルチェックのポイント
さらに、最近では、求人情報をSNS広告で拡散したり、動画・漫画形式のコンテンツを活用するケースも増えています。こうした表現方法においても、消費者(求職者)が事実と異なる内容を信じる可能性がある場合は、不当表示とされる可能性があります。
リーガルチェックのポイントとしては、以下のような視点が重要です。
①募集情報は事実に即しているか(虚偽表示の排除)
②給与・休日・福利厚生などの条件が明確かつ具体的に示されているか
③表現の裏付けとなるエビデンスやデータが存在するか
④法律に基づく表示義務(例:派遣契約に関する明示事項)が守られているか
人材業界における信頼性は、求人広告の正確さに大きく左右されます。 過剰な演出や『釣り広告』のような手法は、短期的な反応を得られたとしても、長期的には企業の評判やコンプライアンスに悪影響を及ぼしますので十分な注意が必要でしょう。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。