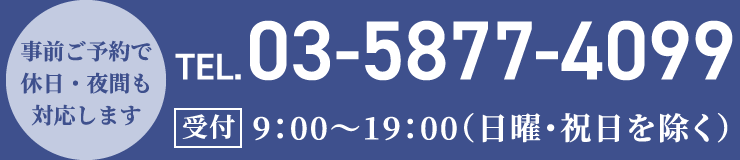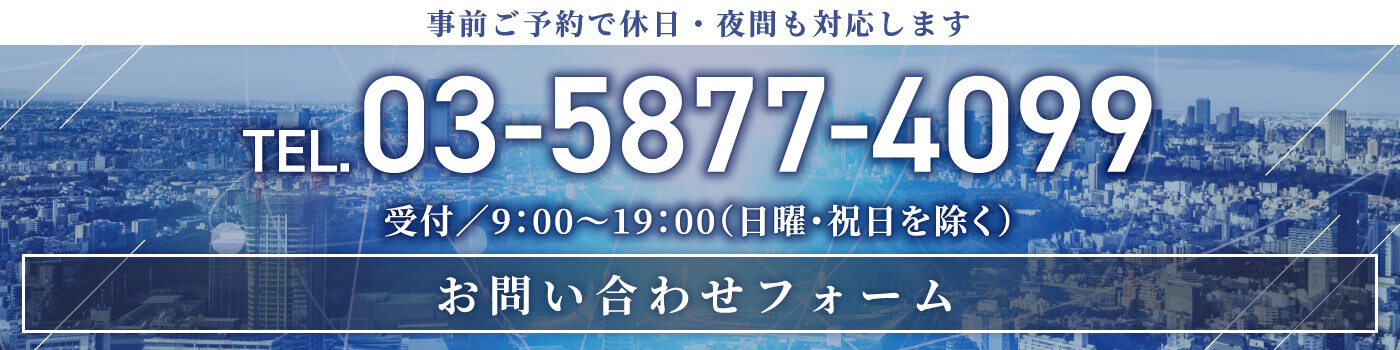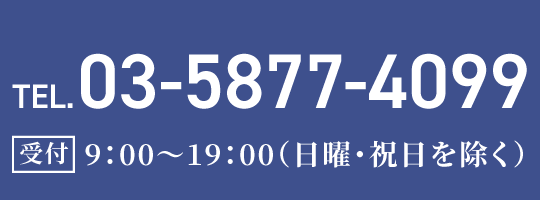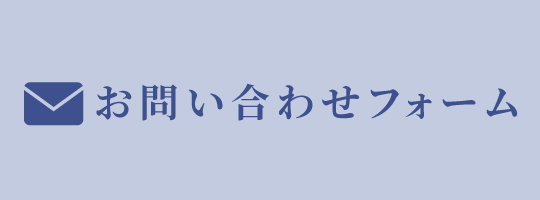Archive for the ‘広告関連法務’ Category
打消し表示の法的有効性:消費者に伝わる表示の鉄則
広告には、スペースや時間の制約から、メインのメッセージを補足したり、条件を限定したりするために、小さな文字やアスタリスクで注意書きを付記することが頻繁にあります。これが打消し表示です。
法務担当者は、「*ただし、効果には個人差があります」といった打消し表示を入れれば、誇大広告のリスクを避けられると考えがちです。
しかし、景品表示法(景表法)の観点から見ると、打消し表示は万能の免罪符ではありません。不適切な打消し表示は、優良誤認表示を解消できず、かえって消費者を誤認に導くとして規制の対象となり得ます。
1 打消し表示の法的限界:「メインの誤認は解消できない」
打消し表示の役割は、メインの表示によって生じた消費者の誤解を解消すること、または重要な前提条件を補足することにあります。
しかし、景表法は、メインの表示がすでに「著しく優良であると誤認させる」レベルに達している場合、打消し表示をもってしてもその誤認は解消されないという立場をとっています。
【具体的なNG例】
メインのメッセージで「誰でも飲めば1週間で必ず-5kg!」と断定的に謳っているとします。これは、科学的根拠がない限り、優良誤認表示(不当表示)に該当します。この下に「*効果には個人差があります」と記載したところで、消費者はすでにメインの断定的なメッセージに強く影響を受けて購入を決断するため、不当表示は解消されないと判断されます。
打消し表示は、誤認が生じない程度の曖昧さや限定的な条件を補足する場合にのみ、有効性を持ちます。
2 打消し表示が有効となるための3つの要件
打消し表示が消費者の誤認を解消し、適法なものとして認められるためには、消費者庁が示す以下の3つの要件をクリアする必要があります。
これらは、「消費者に正しく伝わること」を担保するための鉄則です。
3 法務担当者が注意すべき打消し表示の実務
打消し表示を効果的かつ法的に安全に使用するために、法務部門は以下の実務的なリスクをチェックする必要があります。
(1)リスク1:情報量の多さによる「打ち消し効果の減衰」
打消し表示があまりにも長く、多くの情報を含む場合、消費者はそれを読み飛ばしがちになります。消費者の注意を分散させ、結果として重要な限定条件が伝わらないリスクが生じます。打消し表示は簡潔に、かつ本質的な限定条件のみを記載するようにすべきです。
(2)リスク2:スマホなど表示媒体による差異
パソコン画面では適切に見える文字の大きさや位置も、スマートフォンなどの小さな画面で表示した際に判読が困難になることがあります。すべての表示媒体において、要件2の「視認性」が確保されているかを検証しなければなりません。
(3)リスク3:景表法と特定商取引法との関係
特に定期購入やサブスクリプション広告において、解約条件や総額に関する表示は、景表法だけでなく特定商取引法の規制も受けます。特商法では、「最終確認画面」などにおいて、解除条件や価格に関する情報を誤認のおそれが無いように表示することが義務付けられています。この場合は、景表法の基準よりもさらに厳格な表示の明瞭さが求められます。
4 まとめ:打消し表示は「保険」ではなく「補足」
打消し表示は、あくまでメインの表現が適法であることを前提として、その適用範囲を正確に補足するための手段です。
誇大な広告表現を「免罪符」で合法化しようとする姿勢は、景表法の趣旨に反します。企業の法務担当者や経営者は、広告企画の段階から、客観的な事実に基づいた表現をメインとし、打消し表示は「消費者に正確な情報を提供する」ための最後の確認プロセスと位置づけるべきです。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
口コミ・体験談広告の法的リスク:消費者庁の見解と事業者がすべき対応
インターネット通販やSNSマーケティングにおいて、「お客様の声」や「使用者の体験談」といった口コミ形式の広告は、消費者の信頼を得る上で非常に強力なツールです。
しかし、その信頼性の高さゆえに、景品表示法(景表法)による規制の対象となりやすく、特に法務担当者にとっては注意が必要です。
1 リスク1:優良誤認表示となるケース
口コミ・体験談広告が優良誤認表示(景表法第5条第1号)となるのは、その体験談が商品の品質や効果について、実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる場合です。
これは、体験談が「個人の感想」であるかどうかにかかわらず、事業者が広告として利用する以上、表示責任を負うという原則に基づきます。
(1)根拠のない「最高の効果」の事例
特定の個人が「たった1日で5kg痩せた」「アトピーが完全に治った」といった過度な効果を主張する体験談を、事業者がそのまま広告に利用する場合、優良誤認と判断されます。
【判断のポイント】
①裏付けとなる合理的根拠の有無:事業者は、その体験談の内容が、科学的・客観的な根拠(データ)によって裏付けられる範囲内の効果であるかを、事前に確認する義務があります。
②例外的な効果の強調:多数の人が得られない極めて例外的な効果を、あたかも誰でも得られるかのように強調して表示することは、消費者の誤認を招きます。
(2)打消し表示の限界
優良誤認のリスクを回避するために、「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません」といった打消し表示を付記することが一般的に行われています。
しかし、前回の記事でも解説した通り、メインの体験談が過度な効果を謳っている場合、片隅に小さな文字で打消し表示をしても、消費者の誤認が解消されないと判断されれば、優良誤認表示として規制されます。打消し表示は、あくまで誤認を招く可能性を減らすための補完的な措置であり、広告内容の根拠の欠如を補うものではありません。
2 リスク2:ステマ規制となるケース
2023年10月に施行されたステマ規制(景表法上の指定告示)は、口コミ・体験談広告に対しても大きな影響を与えます。
(1)報酬が発生している場合の明示義務
企業がインフルエンサーやモニターに対して金銭や商品の提供(報酬)を行い、その対価として商品の使用感や体験談を投稿してもらう場合、その投稿は事業者の広告(宣伝)と見なされます。
このような場合、インフルエンサーなどの投稿者は、その投稿が「広告」「PR」「プロモーション」であることを、消費者が容易に判別できる位置に明記する義務があります。この明記がない場合、事業者はステマ規制違反として責任を問われます。
(2)自作自演・第三者装い型
事業者自身や、その従業員が、一般の消費者や匿名アカウントを装って自社商品・サービスの体験談を投稿する行為は、典型的なステマ規制違反です。
これは、事業者による表示であることを隠しているため、消費者がその意見を「公平な第三者の声」と誤認してしまい、「判別が困難な表示」に該当します。
3 投稿内容のモニタリングとエビデンス管理
外部委託先の投稿が、契約通りに広告表示の明記を行っているかを公開後も継続的にモニタリングしましょう。
また、広告に使用する全ての体験談について、その元の投稿内容、投稿者とのやり取り、報酬の有無などのエビデンス(証拠)を、措置命令を受けた際に提示できるよう適切に管理・保管しておくことが、事後的な対応において非常に重要となります。
口コミの力を借りる場合でも、最終的な責任は広告主である事業者が負います。「お客様の声だから大丈夫」という安易な考えは捨て、全ての体験談に「広告責任」が伴うことを認識する必要があります。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
ステマ規制(ステルスマーケティング):事業者が負うべき表示責任と対策の具体例
インターネットとSNSの普及により、企業がインフルエンサーや一般の消費者になりすまして商品・サービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)が問題視されてきました。
このステマが景品表示法の規制対象となり、正式に「不当表示」の一つとして位置づけられました。
企業の法務担当者や経営者は、自社の広告宣伝が意図せずステマ規制に抵触しないよう、この新しい規制の具体的な内容と対策を理解する必要があります。
1 ステマ規制の概要
ステマ規制が目指すのは、「事業者の広告・宣伝であるにもかかわらず、それが広告であると消費者に伝わらないこと」を防ぐことです。
ステマ規制に違反すると判断されるのは、以下の二つの要件を同時に満たす場合です。
①事業者が自己の供給する商品・サービスについて行う表示であること。規制の主体は、広告を依頼・実施する事業者(企業)です。
②一般消費者が、その表示が事業者の表示であることを判別することが困難であること。ここでの「事業者の表示」とは、事業者が自己の利益のために行う広告・宣伝を指します。
重要なのは、規制の対象が「意図的かどうか」ではなく、「消費者が広告だと判別できるかどうか」という外形的な事実に基づいて判断される点です。
2 誰が規制されるのか?事業者の責任の範囲
ステマ規制により責任を問われるのは、広告主である「事業者」です。
インフルエンサーやアフィリエイター(広告の実行者)が、広告主の意図を超えて「これは広告ではない」と虚偽の発言をした場合でも、広告主である事業者が関与・指示をしていれば、責任を免れることはできません。
事業者は、外部の広告代理店やインフルエンサーに業務を委託する際にも、広告である旨の明示(広告表示)が適切に行われるよう、管理・監督する責任を負います。
3 広告だと判別させるための具体的な表示方法
では、消費者に「これは事業者の広告だ」と判別してもらうためには、どのように表示すればよいのでしょうか。
| 媒体 | 望ましい表示方法(例) | NGな表示方法(例) |
| SNS/ブログ記事 | 投稿の冒頭・末尾など目立つ位置に「広告」「宣伝」「PR」「#ad」などと記載する。 | ハッシュタグの中に混ぜる、背景と同化する小さな文字で記載する。 |
| ウェブ記事 | 記事タイトルや記事の冒頭に「[PR]」「〇〇社提供」と明記する。 | 記事の途中の目立たない場所に記載する。 |
4 法務・経営者が取るべき具体的な対策
ステマ規制は、広告活動におけるコンプライアンスのレベルを引き上げました。
景表法違反による措置命令や課徴金のリスクを回避するため、以下の対策を直ちに実行すべきです。
①外部委託先の厳格な管理
インフルエンサーやアフィリエイターと契約する際は、「広告であることの明記」を義務付ける条項を契約書に盛り込みます。さらに、実際に投稿された内容を定期的にチェックするモニタリング体制を構築し、違反が見つかった場合は速やかに是正させることが必須です。
②社内教育の徹底
マーケティング、広報、法務など、広告に関わる全社員に対し、ステマ規制の「意図は関係なく、判別困難なら違反となる」という原則を理解させるための研修を行います。
③広告審査フローへの組み込み
新規の広告案件やインフルエンサー施策を企画する際、法務部門やコンプライアンス部門が、「広告表示の明瞭性・視認性」をチェック項目として組み込み、必ず事前承認を行う仕組みを徹底します。
ステマ規制の導入は、企業に対し、全ての広告活動において透明性と誠実さを求める時代の流れを象徴しています。消費者からの信頼を失わないためにも、法務部門主導で社内の広告審査体制を強化することが、今の経営層に求められています。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
二重価格表示は要注意!「有利誤認表示」の規制内容と適法な表示のポイント
企業の広告において、価格や取引条件の「お得感」を強調することは、消費者の購買意欲を高める上で非常に有効です。しかし、その「お得感」の演出が度を越すと、景品表示法が規制する「有利誤認表示」に該当し、法的な処分を受けるリスクが生じます。
企業の法務担当者や経営者は、価格訴求を行う際に、この有利誤認表示の規制を正確に理解しておくことが不可欠です。
1 有利誤認表示の判断基準
有利誤認表示は、景品表示法第5条第2号に規定されており、価格や取引条件に関して消費者に誤解を与える表示を指します。
具体的には、商品または役務の価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると誤認させる表示を指します。
優良誤認表示との違いは、規制の対象が「価格や取引条件」である点です。例えば、以下のケースが有利誤認の典型例となります。
①価格に関する誤認:実際よりも安い、あるいは他社より安く買えると思わせる。
②取引条件に関する誤認:実際よりも簡単な条件で契約できる、特典が多い、アフターサービスが充実していると思わせる。
2 実務で最も問題となる「二重価格表示」
有利誤認表示の中で、企業が最も注意すべきは「二重価格表示」です。
これは、「通常価格」「メーカー希望小売価格」「〇〇円からの値下げ」などと、現在の販売価格と、それよりも高額な別の価格(比較対照価格)を併記する表示方法です。これにより、消費者は「今買えばお得だ」と感じ、購買行動に結びつきやすくなります。
しかし、この比較対照価格が不当なものである場合、現在の価格が実際よりも著しく安価であると消費者に誤認させるため、有利誤認表示として規制されます。
3 価格以外の取引条件の落とし穴
価格だけでなく、「取引条件」に関する誤解も有利誤認表示となります。特に注意が必要なケースは以下の通りです。
(1)定期購入・サブスクリプションの条件
近年、健康食品や化粧品の定期購入サービスにおいて、有利誤認表示による摘発が多発しています。
①「初回実質無料!」と大きく表示しながら、実は最低〇回の継続購入が必須条件となっている。
②解約条件や解約方法が、広告の目立つ場所ではなく、極めて小さい文字や見えにくい場所に記載されている。
(2)特典・プレゼント(景品規制との関係)
「今だけ限定で豪華特典をプレゼント!」と謳う場合、その特典が実際には提供されなかったり、条件が厳しかったりすると、有利誤認表示となる可能性があります。
また、特典自体が景品表示法の「景品規制」(前回の記事で触れた景品の上限額規制)に抵触しないかどうかも、同時にチェックする必要があります。特典の価格や提供方法によっては、景品規制違反と有利誤認表示違反の両方が成立するケースもあるため、細心の注意が必要です。
4 違反した場合の実務対応
有利誤認表示で景表法に違反した場合、優良誤認表示と同様に、消費者庁による措置命令や、課徴金納付命令の対象となります。
有利誤認表示によるリスクを回避するためには、以下の施策を徹底する必要があります。
①比較対照価格の根拠保管:二重価格表示を行う際は、比較対照価格での販売実績を証明する資料(販売台帳、伝票など)を広告表示の期間終了後も適切に保管する。
②取引条件の明瞭化:定期購入やキャンペーンの条件(継続回数、解約方法、送料、手数料など)は、「誰が見ても誤解が生じない」レベルで、メインの広告に近接した場所で明瞭に記載する。
③審査フローの徹底:広告制作部門は、「お得感」を強調したいあまりに誇張しがちです。価格に関する表示全てについて、必ず法務部門が「根拠の正確性」と「消費者の誤認可能性」の観点から事前にチェックするフローを義務化しましょう。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
「優良誤認表示」の判断基準と事例:商品・サービスの品質に関する嘘を防ぐ方法
企業の広告活動で最も摘発例が多いのが、優良誤認表示です。
優良誤認表示とは、一言でいえば「品質や内容についての嘘や誇張で、消費者に誤解を与える広告」を指します。企業の信頼性を直接損なうリスクがあるため、法務担当者や経営者は、自社広告がこの規制に抵触しないよう、その判断基準を深く理解しておく必要があります。
1 優良誤認表示の判断基準
優良誤認表示は、景品表示法第5条第1号に規定されています。
具体的には、商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示を指します。
この条文に基づき、優良誤認表示が成立するかどうかは、以下の2つの視点から判断されます。
(1)客観的事実との比較:「事実に反しているか?」
広告に記載された品質、性能、効果、原産地、成分などの内容が、実際の商品の客観的な事実と異なっているかを確認します。
単なる「素晴らしい」「最高の使い心地」といった主観的な感想や、曖昧な表現は直ちに規制の対象とはなりにくいですが、以下のような具体的な効果や数値を謳う表現は、その裏付けとなる客観的な証拠が必須となります。
①効能・効果:「シミが完全に消える」「体脂肪が劇的に減る」
②成分・含有量:「高級成分を配合」「天然水100%使用」
③製造方法・産地: 「熟練の職人による手作り」「限定された畑で採れた原料」
(2)消費者の認識:「著しく優良であると誤認させるか?」
表示が事実に反していたとしても、それが消費者に「著しく」優れていると誤認させる程度でなければ、優良誤認表示には該当しません。
しかし、消費者庁は、消費者の商品選択に影響を与える程度の誤認であれば、「著しい」誤認にあたると広く解釈する傾向にあります。
特に、健康や美容に関わる商品の場合、消費者は広告の効果・効能に強く引きつけられるため、誇大広告は「著しい」誤認と判断されやすくなります。
2 法務担当者の最重要チェックポイント:「合理的根拠の提示」
優良誤認表示の規制において、法務・経営者が最も重視すべき実務上のポイントは、「合理的根拠の提示」の義務です。
消費者庁は、広告に記載された効果や性能について、その表示を裏付けるデータや資料(合理的根拠)の提出を事業者に求めることができます。この合理的根拠が提出できない場合、その表示は「不当表示」(優良誤認表示)とみなされ、法違反となります。
3 合理的根拠として認められるための要件
合理的根拠として認められるには、次の2点を満たす必要があります。
①表示された効果・性能を裏付ける客観的な資料があること。
例:専門機関による試験結果、学術論文、業界団体の基準適合証明書など。
②その資料が、社会通念上及び専門的見地からみて、表示内容を裏付けるものと認められること。
例:試験方法の妥当性(被験者数、条件設定、統計処理など)が科学的に認められる水準であること。
「自社に都合の良いデータだけを選ぶ」「試験条件が一般の使用実態と大きく異なる」といった恣意的なデータは、合理的根拠とは認められません。客観的かつ科学的な証明が求められることを肝に銘じましょう。
4 まとめ:経営者がとるべき予防策
優良誤認表示を回避することは、企業の信頼を守る上で最も重要な法務課題の一つです。
経営者や法務担当者は、広告制作部門に対し、以下の点を徹底させる必要があります。
①表示の根拠資料の事前準備:広告に記載する効果・性能は、公開前に必ず客観的な資料で裏付け、それを最低でも3年間は保管する。
②最上級表現の原則禁止:「業界初」「唯一の」「史上最強」など、根拠を示すのが極めて難しい最上級表現の使用は、明確な証拠がない限り避ける。
③法務部門による審査の仕組み化:広告案の最終化前に、表示内容と根拠資料の整合性を法務部門がチェックする社内審査体制を構築する。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
景品表示法(景表法)とは? 法務・経営者が知るべき広告規制の全体像
1 景表法とは?
企業の経営者や法務担当者として、自社の製品やサービスを広く知ってもらうための広告宣伝は不可欠な活動です。
しかし、その広告内容が法的な規制に違反してしまうと、社会的信用を失うだけでなく、多額の課徴金が科されるリスクもあります。
広告規制に関する最も重要な法律の一つが景品表示法(けいひんひょうじほう)、通称「景表法」です。
景品表示法は、「不当な表示」と「過大な景品の提供」を規制することで、消費者が商品やサービスを適切に選べる環境を守り、公正な競争を確保することを目的としています。
この二つの柱について、法務・経営者の視点から基本を理解しておきましょう。
2 不当表示の規制:嘘や誤解を招く広告の禁止
不当表示の規制は、「広告の内容が事実に反したり、消費者に誤解を与えたりすること」を防ぎます。具体的には、以下の3種類の表示が規制の対象となります。
(1)優良誤認表示(第5条第1号)
商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際よりも著しく優れていると消費者に誤認させる表示です。
(例) 実際は他社製品と同じ成分しか入っていないのに、「この製品にしか含まれない特別な成分で驚きの効果!」と謳う、あるいは科学的な根拠がないのに「特許取得で効果保証」と表示するなど。
(2)有利誤認表示(第5条第2号)
商品やサービスの価格、取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示です。
(例)
二重価格表示:実際には販売していない高額な「旧価格」を併記して、現在の価格が安くなっているように見せる行為。
「今だけ無料!」と謳いながら、実際には高額な定期購入が必須の取引。
特に「〇〇%オフ」や「今だけお得」といった価格に関する表現は、比較対照となる価格(元の価格)が客観的に存在し、その表示方法が適切でなければ、有利誤認として規制されます。
(3)その他、誤認されるおそれのある表示(第5条第3号)
代表的なものが、最近規制対象となったステルスマーケティング(ステマ)に関する規制です。
(例) 広告であることを隠して、インフルエンサーや一般消費者のふりをして自社商品を紹介する行為。
ステマ規制により、広告であるにもかかわらず、それが広告(宣伝)であることを分かりやすく表示しない場合、不当表示として規制対象となります。
3 景品規制:行き過ぎた「おまけ」の制限
景品規制は、消費者を誘引するために提供される「景品類」の最高額や総額を制限するものです。過大な景品によって商品の中身ではなく「おまけ」だけで商品選択が歪められるのを防ぎます。
景品規制では、景品の種類や懸賞の方式によって、提供できる景品の上限額が細かく定められています。この上限額を超えて景品を提供すると、景表法違反となります。
4 違反した場合の法務リスクと対応
景表法に違反した場合、企業には以下のような重大なリスクが生じます。
①措置命令: 消費者庁から、違反行為の停止、再発防止策の実施、誤認排除のための周知徹底などを命じられます。
②課徴金納付命令: 不当表示によって得られた売上額に対して一定額に相当する額を課徴金として国に納付しなければなりません。
③社会的信用の失墜: 企業名が公表されるため、ブランドイメージや信用が大きく損なわれます。
法務担当者や経営者としては、「知らなかった」では済まされません。
広告の企画段階から、客観的な根拠の確認や、景品規制の範囲内かどうかのチェックを行うための社内審査体制の構築が急務となります。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
輸入商品・海外製品の広告表示と法的留意点
「海外セレブ御用達!」「アメリカで大人気の商品が日本上陸」「本場◯◯の輸入品」
海外製の商品や輸入雑貨は、その“本場感”や“特別感”を訴求することで高いマーケティング効果を発揮します。しかし、表示内容によっては景品表示法だけでなく、薬機法・食品表示法・不正競争防止法・通関関連法規など、複数の法的リスクが関わってくる分野です。
今回は、輸入商品・海外製品を扱う際の広告表示における実務上の注意点を整理します。
1 「本場」「海外仕様」「正規品」などの表示は要注意
以下のような表現は、一見魅力的に見えるものの、根拠が不明確なまま使うと不当表示とされるリスクがあります。
①「海外セレブが愛用」→ 誰が使っているのか不明、実在しない場合は虚偽表示
②「正規輸入品」「正規代理店品」→ 流通経路や契約関係が明確でなければ誤認表示に
③「アメリカでNo.1の売れ行き」→ 出典・調査機関・調査時期が不明確
④「海外製なので品質も安心」→ 海外製であることと品質の高さの因果関係がないと誤認表示に
このように、“海外”という言葉が印象操作として使われていないかどうかを、広告表示の段階から確認する必要があります。
2 並行輸入品・個人輸入代行の広告は特に慎重に
並行輸入品や個人輸入代行サービスは、正規輸入代理店を通さずに商品を国内で販売する仕組みですが、その表示内容によっては重大な法的リスクが伴います。
①「正規品」「純正品」と表示できるかは、製造元やブランド側との契約関係の有無による
②保証の有無・アフターサービス体制などを明確に記載しないと誤認表示となる
③輸入元が個人または無登録業者である場合、薬機法・関税法違反となるリスクも
また、「輸入品だから安くても安心」といった表現も、品質保証の裏付けがなければ景表法違反の対象となり得ます。
3 リーガルチェックのポイント
①「正規品」「純正品」と表示する根拠となる契約・供給ルートの証拠があるか?
②ランキング表示(例:「アメリカでNo.1」)の出典・調査機関・時期を明示しているか?
③医薬品・サプリ・化粧品などに対して、薬機法に基づく表示確認を行っているか?
④並行輸入品や個人輸入品である場合、その旨を消費者が誤認しないように明示しているか?
⑤日本国内における品質保証・サポート体制についての説明責任を果たしているか?
「海外製」や「輸入品」というワードには、特別感・高品質感を醸し出す力があります。
だからこそ、その表示の裏にある真実・根拠・法令遵守の意識がなければ、企業の信頼は一瞬で崩れる可能性もあるのです。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
健康・美容関連広告の法的境界線
「飲むだけで脂肪が減る!」「塗るだけでシワ改善!」「たった1週間で−5kg!」
こうした健康・美容に関する広告は、消費者の関心が非常に高いジャンルであり、広告効果も大きいため、企業としても積極的に活用したくなる分野です。
しかし、医薬品的な効能をうたった表現や、効果の保証・誇張は、景品表示法だけでなく薬機法(旧・薬事法)にも違反するおそれがあるため、非常に注意が必要です。今回は「ヘルスクレーム広告」における適法表現とNG表現の境界線を整理します。
1 薬機法の対象になる商品とは?
まず前提として、薬機法が規制するのは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の表示に関する広告です。
一方で、サプリメントや健康食品・美容雑貨は「食品」に分類されるため、基本的には薬機法の対象外です。
ただし、たとえ「食品」であっても、広告上で医薬品的な効能効果(疾病の治療・予防・改善)を標榜した場合は、薬機法違反とみなされることがあります。
2 NG表現の典型例(健康食品・サプリ編)
以下のような表現は、薬機法・景表法ともにNGです。
①「これを飲むだけで脂肪が燃える」
②「血圧が下がる/血糖値が改善される」
③「飲めば糖尿病予防になる」
④「薬と併用しなくても大丈夫」
これらは、疾病の治療・予防を暗示しているため、“無承認医薬品の広告”に該当するリスクがあります。また、「飲むだけ」「確実に」などの文言も、再現性を強調しすぎて優良誤認表示とされる可能性があります。
3 NG表現の典型例(化粧品・美容雑貨編)
化粧品や美容アイテムは「医薬部外品」や「雑貨」に分類されることが多く、表現には一定の自由がありますが、“治療効果”を示唆する表現は禁止されています。
①「シミが消える」「ほうれい線が治る」→ 医薬品的効能
②「アトピーが改善される」→ 治療を暗示
③「細胞を修復する」「血流を促進して若返る」→ 科学的根拠の有無が問われる表現
これらも、薬機法違反や景表法による措置命令の対象となった実例が多数あります。
健康や美容に関わる情報は、消費者にとって“切実な期待”を伴うジャンルです。だからこそ、信頼を損なう誇張表現や不当表示は、法的リスクだけでなく、企業のブランドにも深刻なダメージを与えかねません。
“きれいになる”“健康になる”という希望を、事実と根拠をもって、誠実に伝える広告表現こそが、真に選ばれる存在になるのです。
弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
子ども向け広告に求められる表現上の配慮
「遊ぶだけで英語が話せる!」「これがないとみんなに置いていかれるよ」「絶対にゲットしたくなる新商品!」
子ども向けの商品やサービスの広告では、魅力的なキャッチやキャラクターを使って購買意欲を刺激する表現が多く見られます。しかし、判断力が未熟な子どもを対象にした広告には、特別な配慮が求められることをご存じでしょうか?
景品表示法や消費者契約法、さらには業界ごとの自主規制ガイドラインも踏まえて、子ども向け広告で注意すべきポイントを解説します。
1 なぜ「子ども向け広告」は特別な配慮が必要なのか?
子どもは、大人と違い次のような特徴があります。
①表現を額面通りに受け取りやすい
②「買うかどうか」ではなく、「欲しいと思ったらすぐに欲しい」と感じやすい
③価格や条件に対する判断が未熟である
このため、誇張表現やあおり文句、他者との比較を過度に強調する広告は、容易に誤認を招くおそれがあり、景表法や消費者庁の指導対象になりやすいのです。
2 よくあるNG表現
以下のような表現は、特にリスクが高いとされます。
①「これを持ってないと友だちに笑われるよ」
②「いま買わないともう手に入らない!」
③「絶対にモテる」「みんなが欲しがってる!」
④実際の効果や使用感を誇張しすぎているアニメーション演出
これらは、「購入しないと不利益を被る」「今すぐ買わないと損」という誤認を与える表現であり、子どもの判断力を過信した広告表現として問題視されます。
3 景品・おまけ表示も要注意
子ども向け商品の多くに“おまけ”や“抽選特典”がついていますが、以下の点に注意しましょう。
①景品表示法における**「総付景品」「懸賞景品」の金額・数量制限**を超えていないか
②抽選の確率・当選条件などを明確に表示しているか
③「必ずもらえる」などの表現が誤解を招く構成になっていないか
とくに、ゲームアプリやガチャ形式の広告では、排出率の表示や未成年の課金リスクに対して、さらに高い透明性と保護措置が求められます。
4 リーガルチェックのポイント
①誇張表現・過度な演出が子どもの判断を誤らせていないか?
②「買わなきゃ損」「今だけ」など、あおり表現が過剰になっていないか?
③親にねだらせる構成が、圧力的・不適切な誘導になっていないか?
④景品・おまけの表示が法令・業界基準に則っているか?
⑤子どもだけでなく、保護者にも正確な情報が届く設計になっているか?
子どもに向けた広告こそ、「信頼」を軸にした誠実な表現が求められます。
大人のような合理的判断を前提としないからこそ、子どもの目線に立って、安全でわかりやすく、誠実な情報提供を行うことが、社会的信用にもつながります。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
動画広告における演出・表現と誤認表示のボーダーライン
「思わずクリックしたくなる短尺動画」「ストーリー仕立ての感動CM」「インフルエンサーのリアルな体験談」
近年、YouTubeやSNSなどで配信される動画広告は、短時間で視覚・聴覚に訴える強力なマーケティングツールとなっています。しかし、動画という媒体の特性上、演出やテンポ感を重視するあまり、実態との乖離が生じやすく、景品表示法の誤認表示リスクが潜んでいます。
今回は、動画広告特有の注意点と、法的に問題となる表現の境界線を整理します。
1 映像表現でも「広告は広告」──表示規制の対象に
動画広告であっても、文字や画像と同様に景品表示法の規制対象です。特に、以下のような動画構成は注意が必要です。
①前半にインパクト重視の過剰表現を配置し、後半で小さく条件を表示する
②ドラマ仕立てで“あくまで演出”と見せつつ、事実と誤認されるような効果描写を含む
③セリフ・ナレーションで保証や絶対性をうたう表現(例:「これを使えば絶対に改善!」)
広告である限り、“演出だから”では許されません。 消費者がその映像から受ける印象が、実際のサービス内容と食い違う場合、それは「優良誤認表示」とみなされるおそれがあります。
2 ビフォーアフター・実演シーンはとくに注意
動画広告では、「実際に使ってみた」「使ったらこんなに変わった」などの体験型演出や比較演出が非常に多く用いられます。 しかし、それが事実無根の演出や加工である場合、処分対象になり得ます。
よくあるNG例としては、
①実演シーンで、他社製品をあえて不利に扱う(例:音が鳴らないようスピーカーを切る)
②視覚的効果で大幅に変化したように見せるが、映像加工や撮影条件の違いで演出しているだけ
③実在しないユーザーや専門家による推薦・出演
→ これらは、視覚的印象に基づく誤認表示とされ、行政処分に至った事例もあります。
3 誇張表現・再現性のない事例の扱い
①「たった1日でこんなに変わるなんて!」
②「誰でもできる簡単副業で月収50万円」
③「続けるだけで自然に痩せました!」
これらの表現は、個別の体験談であっても、あたかも一般的効果があるかのように見える構成になっている場合、景表法に抵触する可能性が高くなります。
特に動画では、音楽・テンポ・感情的な演出により消費者の印象を大きく左右するため、誇張や曖昧表現には注意が必要です。
動画広告は、もっとも感情に訴える力を持つ広告手法です。そのぶん、消費者を誤認させない「誠実な演出」への責任も大きいということを忘れてはなりません。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。