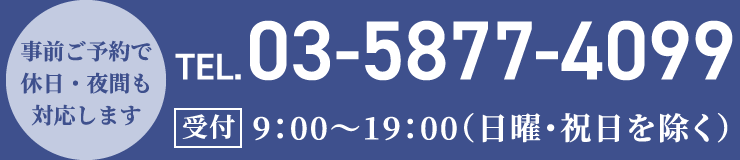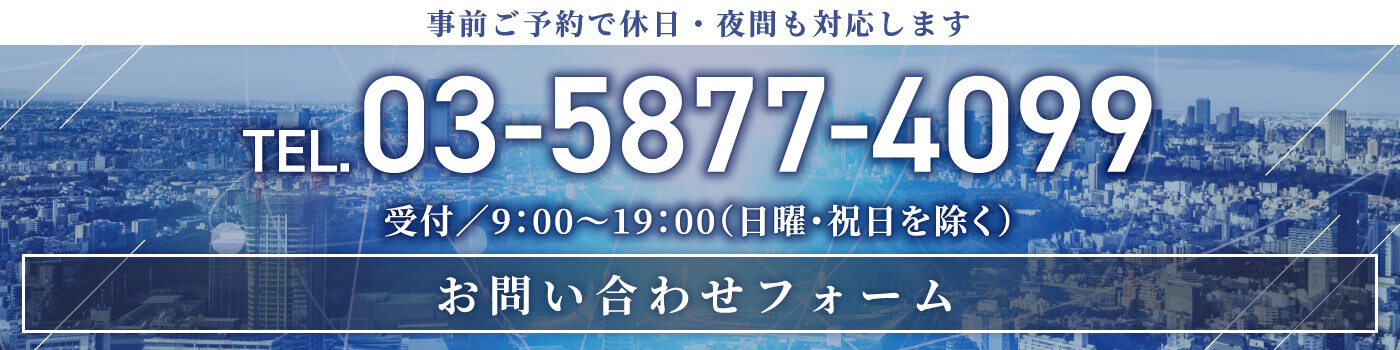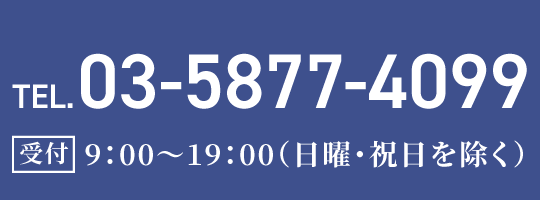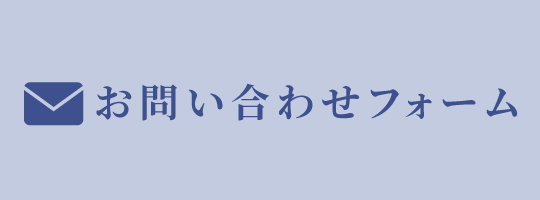「他社より安い」「他社製品より高性能」「従来品と比較して◯%向上
こうした“比較広告”は、商品・サービスの優位性をわかりやすく伝える手段として有効です。しかし、比較の方法や表現の仕方を誤ると、景品表示法違反や不正競争防止法違反に該当する可能性があります。
本記事では、比較広告に関する法的ルールと、実務上の注意点をわかりやすく整理します。
このページの目次
1 比較広告に関する基本ルール
比較広告は、消費者の合理的な選択に資するものであれば許容されるとされています。ただし、次の3つの条件をすべて満たす必要があります(消費者庁「景品表示法に基づく表示に関する公正競争規約等」より)。
①比較内容が客観的事実に基づいていること
②比較方法が公正であること
③他社・他製品を誹謗中傷する内容でないこと
この原則に基づき、広告表現が適切であるかどうかを判断していく必要があります。
2 適法な比較広告の例
①「A社製品と比較して消費電力が30%少ない(当社調べ・2024年3月)」
②「当社のスマホは、同価格帯の他社製品よりも処理速度が平均15%速い(ベンチマーク試験による)」
③「従来品より、吸引力が20%向上(JIS試験方法に準拠)」
これらは、具体的な比較対象・基準・出典・時期が明記されており、かつ客観的な数値に基づいているため、法的にも比較的安全といえます。
3 NG比較広告の典型例
以下のような表現は、景表法違反(優良誤認表示・有利誤認表示)や不正競争防止法(信用毀損)に抵触するリスクがあります。
①「他社製品は古くて時代遅れ。当社だけが最新技術」
②「他社は価格が高すぎる。当社なら激安」
③「B社製品より絶対に効果あり!(根拠不明)」
④「従来品より改善」→ 何がどう改善されたか明記されていない
これらは、事実に基づかない、誤認を招く、または他社を貶める内容であるため、適法性に欠ける可能性が高いです。
4 「従来品との比較」も要注意
比較広告の中でも、「自社の旧モデルと新製品の比較」は比較的使いやすい表現ですが、以下の点に注意が必要です。
①旧製品のスペックやデータを明確に記載しているか?
②新旧製品の条件(使用環境、試験条件等)が揃っているか?
③消費者が誤認しないよう、どの程度の改善かを定量的に記載しているか?
例:「従来品より30%静音化(当社試験による)」はOKですが、「音が気にならなくなった!」のような主観的・あいまいな表現はNGリスクがあります。
比較広告は使い方次第で非常に効果的ですが、「優位性のアピール」と「誤認表示」の間に細い境界線がある表現です。
法的な視点から「比較のしかた」「根拠の出し方」「表現のバランス」を見直すことで、競合と差別化しつつ、信頼される広告を作ることができます。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。