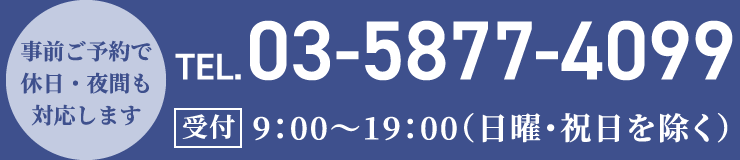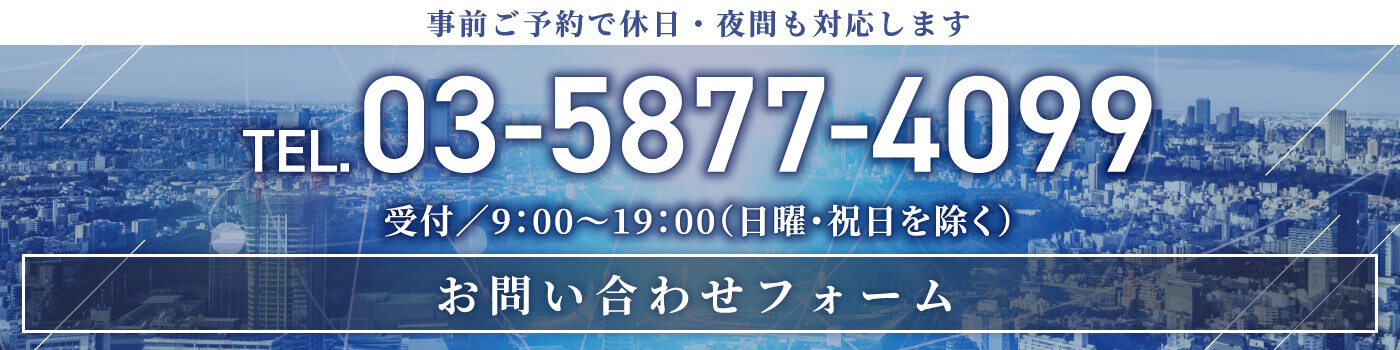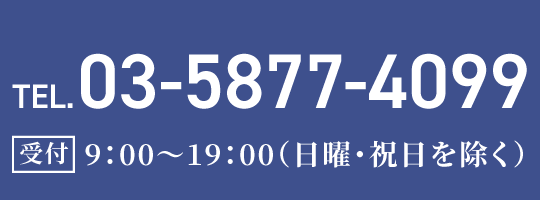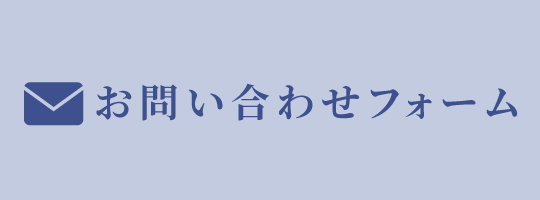「医師監修」「専門家推奨」「〇〇士が推薦!」
こうした表現は、商品・サービスの信頼性を高める強力な広告手法です。特に健康・美容・教育・金融など、専門性が重視される分野で多用されますが、実態に伴わない表示を行うと、景品表示法違反や業法違反に該当するリスクがあるため、慎重な運用が求められます。
このページの目次
1 「医師監修」は何を意味するのか?
「監修」とは一般的に、「内容の正確性や専門性について確認・指導すること」を指します。よって、「医師監修」と表示する場合には、実際に医師が内容確認・指導を行っている事実がなければ、虚偽表示や優良誤認表示とみなされる可能性があります。
たとえば以下のような表示には注意が必要です。
①一度だけ意見を聞いただけで「監修」と表示
②医師の関与が古く、現行の内容に影響していない
③名義貸し的に名前だけを使っている
これらは、「監修」と呼ぶには不十分な関与である場合、誤認を与える表示(景表法違反)とされるおそれがあります。
2 「専門家推奨」の場合も根拠が問われる
「〇〇士が推奨」「管理栄養士も推薦」「金融のプロが勧める」といった表現もよく見られますが、これも“誰がどのような根拠で推薦しているのか”が明示されていない場合には、優良誤認表示のリスクがあります。
注意すべきポイントとしては、
①実在の専門家が明確な根拠を持って推薦しているか?
②実際に使用した上での推薦か、それとも金銭的契約によるものか?
③複数の専門家の声を使っている場合、全員の同意・監修実績はあるか?
特に、報酬を受け取って推薦している場合には、ステマ規制の対象にもなるため、「広告表示の明示」が必要になるケースもあります。
「医師も推薦!」「専門家も納得!」など、抽象的な表現は具体的な関与が不明確であり、誤認の原因となります。消費者が、「あたかもその専門家全員が製品の品質を保証している」かのような印象を持つような表示は、避けなければなりません。
3 広告表示の文脈も重要です
また、表示に医師や専門家の顔写真・氏名・肩書きを使用する場合には、本人の許諾を得るとともに、表示する内容の正確性や現在性(最新性)を担保することも必要です。
4 リーガルチェックのポイント
①実在の医師・専門家か? 表示内容について本人の監修・同意があるか?
②推薦の根拠・内容が明確かつ客観的に説明できるか?
③使用している顔写真・肩書き等が事実と相違ないか?
④製品が薬機法対象かどうかを確認済みか?
⑤報酬提供がある場合、「広告表示」がなされているか?(ステマ対策)
「医師監修」「専門家推薦」は、適切に使えば大きな広告効果がありますが、その“信頼性”こそが、最も厳しく問われる表現でもあります。
一時的な訴求力ではなく、長期的に信頼されるブランドを築くためにも、法令遵守に基づいた慎重な運用が必要です。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。