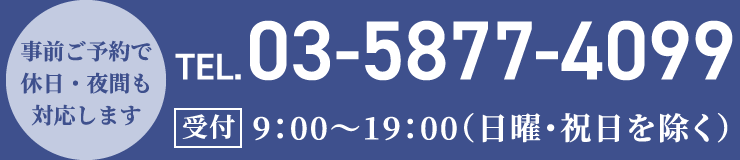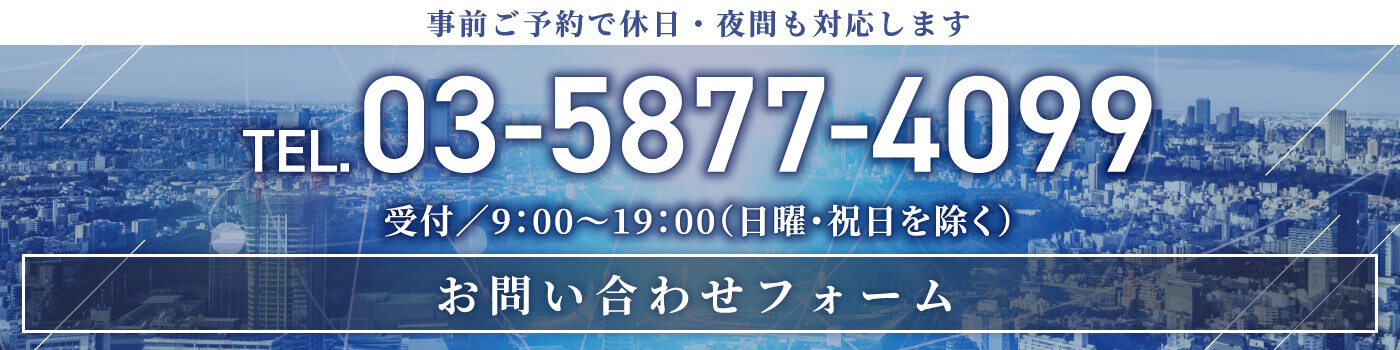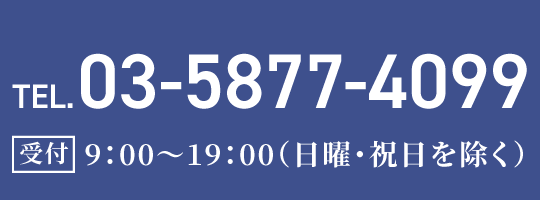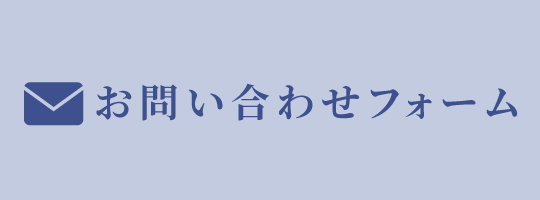「〇〇を使って人生が変わりました!」「たった1週間で効果を実感!」「家族にも勧めています」
こうした体験談や口コミは、企業が自ら語るよりもはるかに説得力を持つため、広告や販促において非常に効果的です。しかし、消費者に誤解を与えるような使い方をすると、景品表示法違反(優良誤認表示)やステマ規制に抵触するリスクがあるため、注意が必要です。
このページの目次
1 体験談も「表示」として景品表示法の対象になる
景品表示法では、企業が行う広告表現において「実際のものより著しく優良である」と消費者に誤認される表示は禁止されています。そして、体験談・口コミも広告内で使えば“表示”としてこの規制の対象となります。
特に以下のような使い方はNGの典型です。
①個人の体験談を紹介しつつ、それが誰にでも再現できるかのように見せる
②一部の好意的意見だけを抜粋して表示し、実態より良い印象を与える
③実在しない人物による架空の体験談を掲載する
④効果に関する記述に科学的根拠がない(例:「2週間でウエスト5cm減」)
このような表現は、広告主の責任において根拠資料の保存・説明が求められ、行政処分の対象となるおそれもあります。
2 ステマ規制の適用対象にも注意
2023年の景品表示法改正により、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)が表示規制の対象に明確化されました。企業が報酬を支払って提供された体験談や口コミを、あたかも第三者の自然な発信であるかのように見せることは、違法表示とされる可能性があります。
特に次のような場合には注意が必要です。
①無料提供したモニターの声を「一般の顧客の感想」として表示する
②インフルエンサーに報酬や商品を提供して投稿してもらいながら、「#PR」「広告」といった明示をしていない
③企業が内容を監修・編集している口コミを、“自主的投稿”のように扱う
これらはいずれも、「広告であることがわかるように表示していない」=不当表示とみなされる可能性があるため、表示の明確化が必須です。
3 「あくまで個人の感想です」で済むのか?
体験談の末尾によく使われる「※個人の感想です。効果には個人差があります。」という文言は、一定の補足としては有効ですが、これだけで全ての誤認リスクが免除されるわけではありません。
広告の中心的部分に体験談が据えられている場合には、たとえ「個人の感想」だと明記していても、消費者が“一般的効果がある”と誤認すればアウトとなる可能性があります。
4 リーガルチェックのポイント
体験談・口コミを広告に使う場合のチェックリストとしては、
①実際にそのような体験があったか、事実確認と本人の同意を取っているか?
②表示されている内容に、合理的根拠資料が存在しているか?
③再現性のない成功事例を、一般化した表現にしていないか?
④報酬提供がある口コミ・投稿に、「広告」「PR」の表示がなされているか?
⑤「個人の感想」表示が免罪符になっていないか?
体験談・口コミは信頼性の高い訴求手法である一方、広告としての責任が非常に重い表現でもあります。「誰が」「どのような立場で」「どんな意図で語っているのか」を明確にし、誠実なコミュニケーションを心がけることが、法的トラブルの予防にもつながります。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。