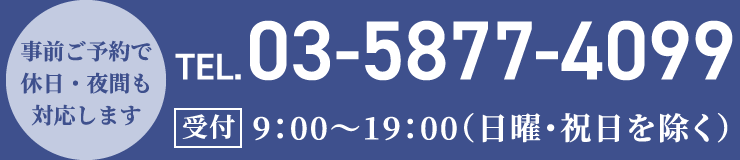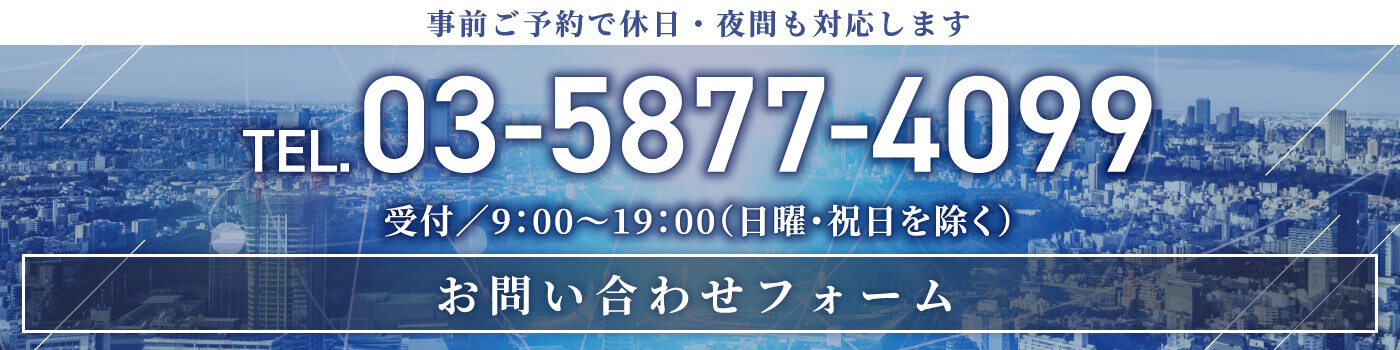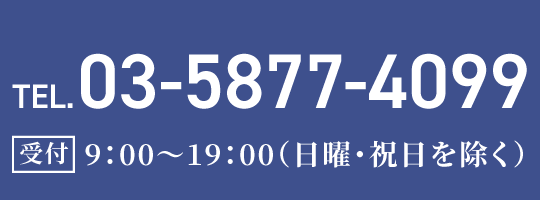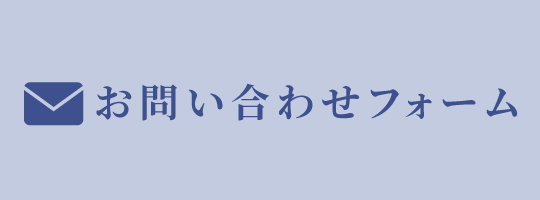「業界No.1」「売上シェア国内トップ」「お客様支持率No.1」
こうした“ナンバーワン”表現は、企業や商品の信頼性・実績を強く印象づける効果があります。しかし、その分、景品表示法上の違反リスクも高く、慎重な運用が求められる広告表現です。本記事では、「No.1表示」「シェア表示」に関する法的リスクと、適法な表示のポイントを解説します。
このページの目次
1 「No.1」表示の根拠が求められる理由
「No.1」は、他の事業者との相対的な優位性をアピールする表現であるため、景品表示法における「優良誤認表示」に該当するか否かが常に問われます。
たとえば、以下のような表示はリスクがあります。
①調査期間や母集団が極端に限定されている
②出典が不明で、消費者が根拠を確認できない
③実際には僅差であり「No.1」と言えるか疑問な数値差
④売上高ではなく広告出稿量など別指標での“1位”を、総合的な優位と誤認させる表現
これらは、調査主体・調査範囲・期間・指標の不明確さによって、消費者に実態以上の印象を与えるおそれがあるため、違反とされる可能性があります。
2 「No.1」表示に必要な3つの原則
①根拠資料が存在すること(客観的データ)
第三者機関の調査結果や、売上統計、POSデータ、特許庁の登録数など、明確な数値データに基づく資料が必要です。
②比較対象・調査母体が適切であること
全国規模の商品であれば、全国の競合を対象にした調査でなければ意味がありません。「自社調査」や「一部地域のデータ」でのNo.1表示は、注意が必要です。
③表示内容に誤認を与える要素がないこと
調査項目・調査方法・期間・対象などを広告内で適切に開示し、消費者が「なぜNo.1なのか?」を判断できるようにすることが求められます。
3 「シェア表示」との違いと注意点
「No.1」と似た表現に「シェア〇%」「業界シェアトップ」などがあります。これも景品表示法上の“相対比較表示”にあたるため、No.1表示と同様に根拠が必要です。
特に注意すべきポイントとしては、
①「市場シェア」の定義を広告内に明記しているか?(例:販売金額ベース、販売数量ベース)
②対象市場が適切か?(例:「〇〇市場」での1位だが、他の競合を除外していないか)
③数字の単位や出典が明記されているか?(例:「矢野経済研究所調べ 2023年」など)
4 リーガルチェックのポイント
①表示している「No.1」に客観的なデータと出典の明示があるか?
②調査の対象期間・方法・母数が明確で、開示されているか?
③「シェア表示」の場合、市場定義・単位(売上数/金額)が正確か?
④広告の文脈から、消費者が不当に誤認しない表現となっているか?
「No.1」表示は、非常に強い訴求力を持つ表現ですが、それゆえに、景表法の厳しい審査対象となる“ハイリスク表現”でもあります。
適切な根拠と表現のバランスをとることで、安心して活用できる“信頼あるナンバーワン”を実現しましょう。 弊事務所では広告法務に関して総合的にサポートを提供しております。広告法務に関してお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。