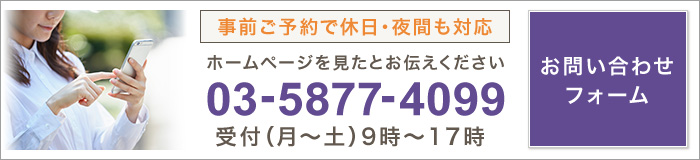生成AIの急速な普及により、文章・画像・音楽・プログラムなどのコンテンツが誰でも簡単に生成できる時代が到来しました。しかしその一方で、生成AIが著作権保護された既存作品を無断学習・模倣しているのではないかという懸念が広がっています。本記事では、生成AIと著作権の交差点で生じる法的論点と、実務上の注意点について解説いたします。
このページの目次
1 「学習」行為は著作権侵害になるか?
AIが著作物を利用するタイミングとして主に問題となるのは、「学習」と「出力」の2段階です。
まず、学習については、著作権法第30条の4により、情報解析のための著作物の利用(いわゆる「テキスト・データマイニング」)は一定の場合に許容されるとされています。この規定により、非営利かつ限定的な目的であれば、許可なく著作物をAIに学習させることが可能とされています。
しかし、営利目的のサービスや大規模データセットの構築にあたり、著作物を網羅的・継続的に取り込む行為が「著作権の濫用」と評価される可能性もあり、今後の判例動向が注目されます。
2 出力結果に他人の著作物が含まれている場合
実務上特に問題となるのが、AIが生成したコンテンツに、既存の著作物と酷似する内容が含まれている場合です。たとえば次のようなケースが考えられます。
①有名漫画の画風や構図を再現した画像生成
②特定の小説の登場人物やセリフを再構成した文章生成
③人気楽曲とほぼ同一の旋律を含むAI作曲
このような生成結果が既存著作物の「翻案(=改変的利用)」に該当する場合、著作権侵害と評価される可能性があります。
3 実務対応:利用者が注意すべきポイント
①生成物の商用利用には慎重になる
とくに類似性が懸念される作品(アニメ・漫画・楽曲等)に類似する内容を使う場合は、事前に著作権者の許諾を得るのが安全です。
②生成サービスの利用規約を確認する
ChatGPT、Midjourneyなどの生成AIサービスには、「出力物に関する権利関係」「利用者の責任範囲」などが記載されています。
「利用者が出力内容の合法性を確認する義務がある」と明記されているケースが大半です。
③他人の著作物に似ていると感じたら使用を控える
微妙なケースでは、著作権法の「依拠性」「類似性」判断が必要になります。著作権に詳しい専門家の意見を仰ぐのが適切です。
生成AIはクリエイティブな可能性を大きく広げるツールですが、それゆえに**「何を参考にして生成されたか分かりにくい」リスクを内包しています。
生成されたコンテンツがたとえAIによるものであっても、最終的に責任を問われるのは利用者自身です。トラブルを避けるためには、生成物の内容と出典を常に意識し、利用目的に応じた法的確認を怠らないことが重要です

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。