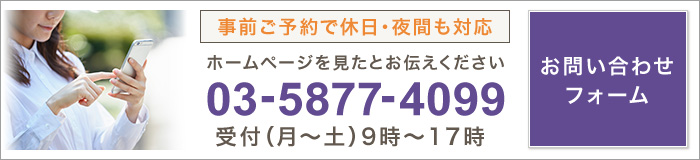Googleマップや食べログ、楽天レビューなど、口コミ投稿がビジネスの集客や評価に直結する時代。好意的なレビューが集まれば売上が伸びる一方、虚偽や悪意あるレビューによって風評被害を受ける事業者も少なくありません。今回は、ネット上に投稿された悪質レビューへの法的対処法を、実例とともに解説いたします。
このページの目次
1 悪質レビューとは?
口コミ自体は表現の自由の範囲内ですが、次のような投稿は違法性を帯びる可能性があります。
①事実無根の内容(「虫が出た」「異物が入っていた」等の虚偽)
②利用していない者による投稿
③競合他社などによる営業妨害目的の書き込み
④過剰に侮辱的な表現(「最低の店」「人間のクズ」など)
これらは名誉毀損、信用毀損、業務妨害など、刑事・民事両面の違法行為に該当する可能性があります。
2 裁判例:虚偽レビューによる損害賠償命令
ある裁判例では、実際に来店していない人物が飲食店に対し、「不衛生」「態度が悪い」といった虚偽のレビューを投稿した件について、裁判所は名誉毀損を認定。投稿者に対して50万円の損害賠償命令を下しました。
この裁判例では、利用実績のない者による虚偽の投稿が「営業上の信用・評価を著しく傷つけた」と評価されました。
3 プラットフォームへの削除申請
多くの口コミサイトや検索エンジンでは、ガイドライン違反に該当するレビューについて削除申請が可能です。以下のような文言で申請を行うと、削除される可能性が高まります。①「虚偽の内容であり、営業妨害を受けている」
②「実際に来店・利用された形跡がない」
③「競合店舗と思われる人物による悪意ある書き込みである」
申請には投稿内容の具体的な反論や、営業記録などの証拠が添付されると効果的です。
4 投稿者の特定と損害賠償請求
悪質なレビュー投稿者が匿名の場合、発信者情報開示請求によって投稿者のIPアドレスや契約者情報を取得し、損害賠償請求を行うことが可能です。請求には以下のような根拠が用いられます。
①民法709条に基づく不法行為責任(虚偽による名誉毀損・信用毀損)
②刑法230条、233条に基づく刑事責任(名誉毀損罪・業務妨害罪)
裁判を通じて削除と損害賠償を同時に請求することも可能です。
事業者にとってネットレビューは「集客と信頼の命綱」ともいえる存在です。虚偽や悪意のあるレビューを放置すれば、検索結果や評価スコアに悪影響が残り続け、長期的に顧客離れにつながる恐れがあります。
一方で、すべての批判的レビューが違法になるわけではありません。あくまで**「真実に反する」かつ「不当に評価を落とす内容」であるか**がポイントになります。
悪質なレビューを発見した場合は、まず冷静にスクリーンショット等の証拠を確保し、プラットフォームへの削除申請を行うと同時に、必要に応じて弁護士への相談をおすすめします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。