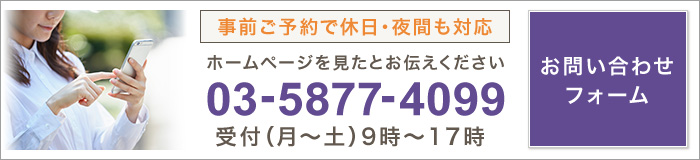SNSや口コミサイト、掲示板などで企業名や商品名が取り上げられることが日常となった現代において、虚偽の情報が一度拡散されると、企業にとって深刻なダメージとなり得ます。本記事では、ネット上での虚偽風評が企業に与える影響と、それに対する法的対応の在り方について解説いたします。
このページの目次
1 企業に対する虚偽風評の典型例
企業に関するネット上の虚偽情報には、以下のようなものがあります。
①「○○社は過去に倒産寸前だった」などの事実無根の噂
②「この製品は人体に有害」といった科学的根拠のない投稿
③「社長がパワハラを繰り返している」など名指しでの誹謗中傷
④「この会社は詐欺をしている」といった犯罪行為の示唆
これらの情報が検索結果やレビューとして残り続けると、顧客離れや採用活動への悪影響、株価下落など、企業活動全般に大きな損害を与える可能性があります。
2 法的対応の選択肢
①削除請求
投稿先が明らかであれば、まずは運営者に対して投稿の削除を求めることが基本となります。削除の根拠としては、名誉毀損、業務妨害、信用毀損などが挙げられます。
②発信者情報開示請求
投稿者が匿名であっても、プロバイダ責任制限法に基づいてIPアドレス・契約者情報の開示を求めることが可能です。これにより、損害賠償請求へと進むことができます。
③損害賠償請求・謝罪広告請求
虚偽の情報によって企業の利益や社会的信用が毀損された場合、投稿者に対し損害賠償や謝罪広告の請求が可能です。企業名や役員個人名への中傷は、名誉毀損として違法性が高く判断されやすい傾向にあります。
3 裁判例:掲示板への書き込みと賠償命令
ある裁判例では、掲示板において「○○社は違法な営業をしている」といった書き込みがなされ、投稿者に対し100万円の損害賠償が命じられました。裁判所は、投稿内容が真実であるとの立証がなされず、かつ公共性や公益目的も認められないとして、名誉毀損の成立を認定しました。
この裁判例では、企業が虚偽風評に対して法的措置をとることの実効性を裏付けるものです。
企業にとって、ネット上の風評管理はもはや「リスクマネジメント」の一環です。放置すれば拡散・検索結果の上位表示といった形で悪影響が拡大してしまいます。
問題となる投稿を発見したら、削除・発信者特定・損害賠償請求の可否を含めて、専門家に早期相談することが重要です。場合によっては、事前に風評対策を講じるための法的助言や体制整備も効果的です。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。