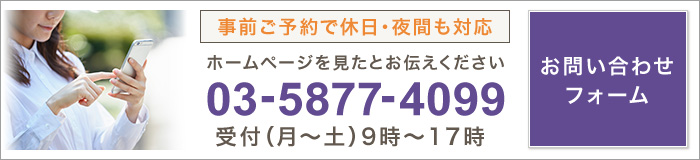本日は、新型コロナウイルス感染拡大の中で虚偽の情報が拡散され、個人の名誉が侵害された事案に関する裁判例をご紹介いたします(大阪地判令和6年2月22日)。
このページの目次
1 事案の概要
原告は、高級クラブに勤務をしている方(通称「D」)です。
被告Aおよび被告Bは、匿名掲示板において、有名芸能人が新型コロナウイルス感染後に亡くなった原因が、原告であると示唆する投稿を行いました。
原告はこれらの投稿によって自身の社会的評価が低下し、精神的苦痛を受けたとして、被告らに対し損害賠償を請求しました。
2 裁判所の判断
(1)名誉毀損の成立
裁判所は、一般的な読者の注意と読み方を基準にして、両名の投稿はいずれも具体的な事実を示すものであり、原告の社会的評価を低下させ、名誉毀損にあたると判断されました。
(2)損害額の認定
裁判所は以下の内容を考慮し、被告AおよびBそれぞれに対し12万円の損害賠償を認めました。
①投稿内容が虚偽であり、原告に精神的苦痛を与えたこと。
②ただし、同様の噂がすでにインターネット上に広まっていたことから、投稿の影響は限定的であった。
③原告が特定するための調査費用および弁護士費用として2万円も加算。
3 インターネット上の投稿にはご注意ください
本件は、インターネット上の匿名掲示板の投稿が名誉毀損にあたるか否か、特に「匿名性」と「疑問形の表現」に焦点が当てられた事例です。
被告Bの投稿は「感染したのか」という疑問形でしたが、裁判所は投稿前後の文脈やスレッドの流れを考慮し、「事実を示唆する内容」と判断しました。疑問形であっても、名誉を傷つける内容であれば名誉毀損が成立しうる点は重要です。
また、被告らは「掲示板の閲覧者数が少ない」、「信憑性がない」等と主張しましたが、裁判所は「誰でもアクセス可能であること」「内容が著名人の死因に関わる重大な事実を示唆するもの」であることを重視しました。匿名の投稿であっても、不特定多数に広まる可能性がある限り、法的責任を免れることは難しいと示されました。
インターネット上の情報発信は手軽である一方、その影響力と責任は決して軽視できないものです。個人の名誉を傷つける投稿は法的責任を負うリスクがあることを再認識し、正確な情報発信を心がけることが重要です。 インターネット上のトラブルに何らかの形で巻き込まれてしまった場合には、まずは専門家にご相談いただき、冷静な対応を心がけることが重要です。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。